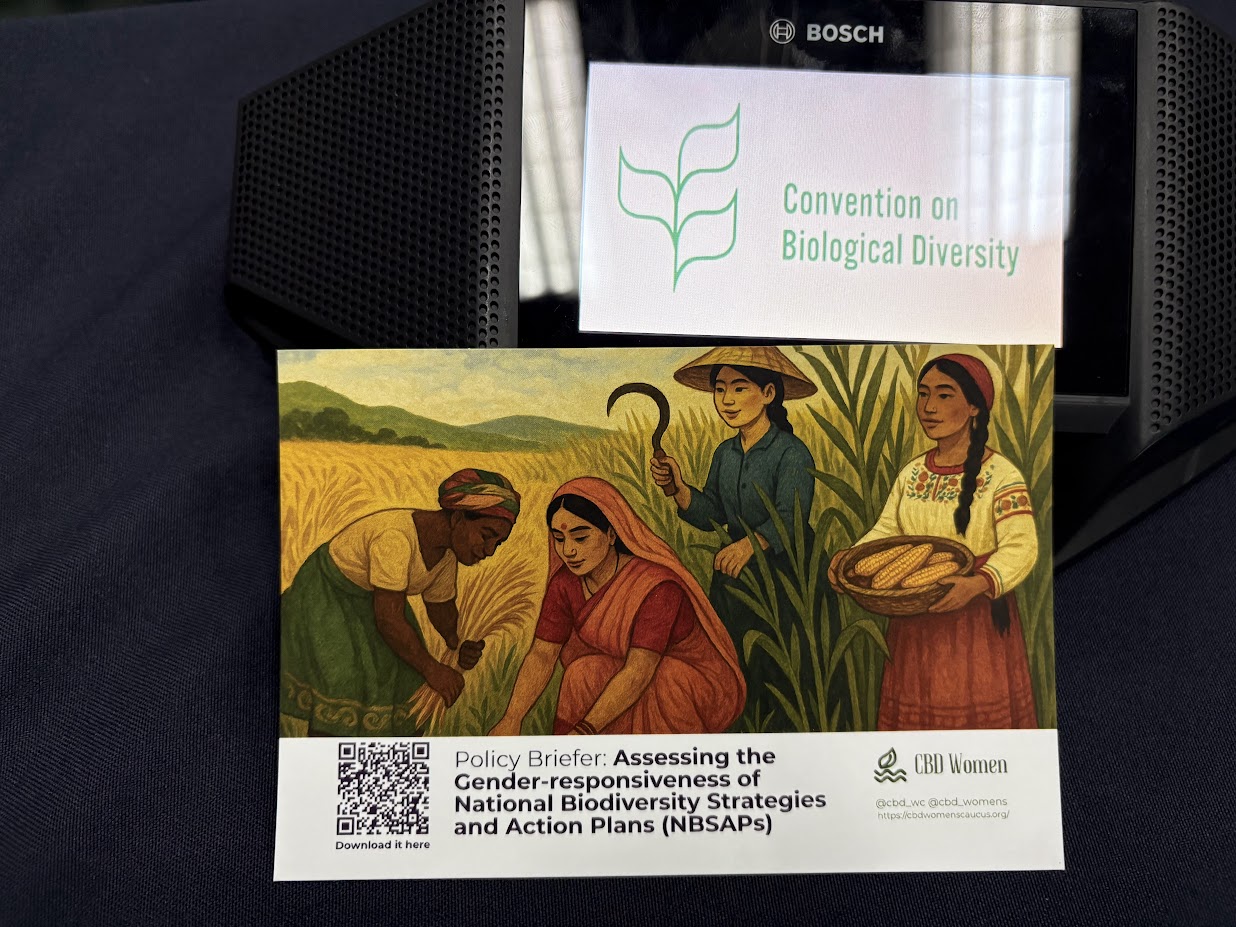生物多様性条約(CBD)の科学技術助言補助機関会合(SBSTTA)は、生物多様性政策と科学的知見をつなぐ場であり、昆明・モントリオール生物多様性枠組(KM-GBF)の実施状況を把握し、今後必要となる行動へ助言を提供する役割を担っています。
会議参加者に向けて公開された参加者リストによると885名が登録していました。NGOの意見交換では、2026年2月にローマで開催予定の条約の実施に関する補助機関会合の方が注目が高く、参加も多いのではないかという見通しを示す方もいました。肝心の中身について、SBSTTA27では、GBFの進捗評価のためのグローバル報告書の在り方、IPBESの最新知見の活用、気候危機と生物多様性との関係、GBFと既存プログラムの整理や新規事業の検討、外来種対策、農業と健康など、幅広い議題が議論されました。
SBSTTA27は、延長の末、最後には同時通訳もなくなり英語だけで会議が進展。時間がないことからSBSTTA起点の文案を削除することも多数起きました。「一つの国の反対で決定がゆがめられたことを報告書に正式に記載してほしい」と述べる国もありました。COP15で意欲的なGBFを策定以降、議論するべきことが多すぎて補助機関会合がパンクをしている様子は今回も続いた形です。
本稿では、議題3から議題10のCOP17に提案された勧告案と残された課題を報告します。本題に入る前に、世界中から交渉官を集め、5日間をかけて会議が行われましたが、協議・コンタクトグループの時間は議題に対して圧倒的に少なく(あるいは、合意に向けた歩み寄りの精神(Spirit of Compromise)が少なく)、あらゆる文章にあちこちに非同意事項の[ ]がかかっており、非常に読みにくい文章になっています。
議題3:グローバルレビュー(KM-GBFの進捗評価)
本議題では、KM-GBFの進捗を評価する(グローバルレビュー)に影響力をもつ報告書の構成が議論されました。報告書は、第7回国別報告書(2026年2月提出)および各国のNBSAP(国家生物多様性戦略)を基本情報源としつつ、その他COP16の第32決定に基づき、各国ごとの評価ではなく、世界全体としてどれだけ前進したかを集約的に捉えるという点が再確認されました。途上国からは、このレビューの結果として途上国に対する新たな努力目標が課されることへの警戒がにじみ出る発言が多く聞かれた印象です。
本体決定部分では、締約国には、2026年2月末までに第7回国別報告書を提出すること、また、NBSAP未更新国は提出を急ぐことが強く促されました。さらに、事務局は、国別報告書の提出支援、先住民・女性・若者を含む多様な主体からの貢献情報の収集、技術対話の場の提供を行うことが求められました。
付属文書では、
- 生物多様性の現状とトレンド
- GBFの実施状況(NBSAP、2030ターゲット、2050ビジョン、実施手段、他の環境条約)
- 結論とキーメッセージ
という3部構成が示されました。
期間中に、先住民・女性・若者など非国家主体の貢献も体系的に反映できるよう、オンラインレポーティングツールが更新され、非国家主体の貢献を入力できるようになったことが発表(Notification)されました。
議題4:IPBESの最新評価が示す知見の活用
IPBESは「生物多様性・水・食料・健康・気候の相互関係(ネクサスアセスメント)」と、「生物多様性損失の根本原因と社会変革(トランスフォーマティブ・チェンジアセスメント)」という2つの主要アセスメントを公表しています。
SBSTTA27では、これらの知見を昆明・モントリオール生物多様性枠組(KMGBF)の実施に反映させる必要性が共有され、特に 生物多様性政策を“自然科学の問題”にとどめず、社会構造・経済制度・意思決定への変革の問題として扱うことが強調されました。相変わらず、IPBESからの報告書を「歓迎する」か「留意する」かで争うなど、科学技術助言機関としての価値を疑う、ポリティカルなやり取りが展開された議題です。
成果文書のポイント(何を決めたか)
COP17 で、IPBES「ネクサス評価」と「トランスフォーマティブ変革評価」を[歓迎][留意」することを勧告。
締約国に対し、水・食料・健康・気候と生物多様性の相互作用に基づく政策統合(ネクサス・アプローチ)を推進することを奨励。生物多様性損失を引き起こす要因を変えるため、公正・包摂・多様な価値観を尊重した意思決定を進めることを奨励(トランスフォーマティブ・チェンジ)。
先住民族・地域共同体、女性・若者、民間セクターを含む 多様な主体の参画を政策形成過程に組み込むことを明記。
事務局は、各国の経験共有の場を設け、ガイダンス作成や普及啓発にIPBES評価結果を活用するよう要請する文案をまとめました。
議題5:気候変動と生物多様性
気候変動と生物多様性損失は相互に影響し合う危機であり、両者に同時に対応する政策が不可欠です。
SBSTTA27では、自然に根差した解決策(NbS)または生態系ベースアプローチ(NbS / EbA)の取り組みを強化するため、既存の「生態系に基づく適応に関する自発的ガイドライン」に対する補足文書(Primer for Policymakers)の改訂方向が議論されました。
COP17に向け文書をさらにブラッシュアップすること、また、生物多様性条約(CBD)・気候変動枠組条約(UNFCCC)・砂漠化対処条約(UNCCD)の3条約間連携を強化するため、活動、指標、モニタリング、報告等を含む、条約間の政策整合性を高める重要性が確認され、条約事務局、科学補助機関、議長国間の情報交換の開催等を要請することとしました。
一方、COP17勧告案は、合意できてないことを示す[ ]で囲まれた表現が多く、COP17での合意文書作成に向けたたくさんの課題をCOP17本番に先送りしたような形になっています。
成果文書のポイント(何を決めたか)
- 締約国に対し、気候・土地利用・生物多様性政策を統合する「ネクサス的アプローチ」を促進するよう奨励。
- IPLC(先住民・地域共同体)、女性・若者などの権利と参加を保障する社会・環境セーフガードの強化を明記。
- CBD・UNFCCC・UNCCD、締約国、その他の機関に対して改定予定の自発的ガイドラインの活用を要請。
- 自然に基づく解決策への投資拡大について、政府および民間金融機関への協力を呼びかけ。
などの勧告案が作成されてはいるものの、ほとんどに[ ]が入っており、何も決まってないといった方が正確です。
議題6:既存プログラム(PoW)の整理・更新・新規領域の検討
SBSTTA27では、生物多様性条約がこれまで発展させてきた多数のテーマ別作業計画(Programmes of Work:PoW)および横断的作業領域を、昆明・モントリオール生物多様性枠組(KM-GBF)に沿って整理・統合する方向性が議論されました。長年蓄積されたPoWの中には、依然有効なもの、新たな枠組に合わせて更新が必要なもの、他分野と統合した方が有効なものなどが混在していることが指摘され、重複を減らし、実施の一貫性・効率性を高める必要性が共有されました。
成果文書のポイント(何を決めたか)
COP17および第7回条約の実施に関する補助機関会合に向けて、戦略レビュー、(見直しが必要と判断したテーマの)見直しスケジュールなどを整理することを求めました。
検討作業は今後も続けられることから、COP17勧告案は、マルっと全体が[ ]非合意事項扱いです。文案としては、既存PoWの分類-維持・更新・統合・外部主導へ移管することを決定することが読み取れます(予定)。既存の案は、事務局が、KM-GBFとの整合性を踏まえ、示した整理案がそのまま文案に反映されています。(COP17に向けたプロセス次第で、内容の変更があります。いずれにしても、COP17へ提出予定)。
- 維持するプログラム :森林、島嶼、海洋沿岸、侵略的外来種、保護地域、モニタリングなど 既存ガイダンスが依然有効、継続更新で対応
- 更新が必要なプログラム:農業生物多様性、内陸水域、山岳、世界タクソノミーイニシアティブ(GTI)、生態系回復
- 統合が適切な領域:主流化、経済・貿易、持続可能な利用、ビジネス関与、技術協力、資源動員 等
- 外部が主導する領域へ移管:文化・生物多様性連関、乾燥地、影響評価手法 等
② 森林PoWについては、補足行動案(Annex)が提示
森林生物多様性PoWについては、保全・回復・持続可能な林業管理の具体的行動リストを作成する方針で、継続協議となりました。
③ 新規のテーマについては、生物多様性を加味した空間計画、汚染、人権ベースアプローチ、多様な価値に基づく対策の4テーマが検討されましたが、国連内で様々な協議が検討されている(ex. 汚染に関する専門パネルの構築など)こともあり、締約国の共通見解の構築が現時点で難しいことから、汚染に関する政府間パネル含む国際機関への情報収集の上、第28回SBSTTA(2026年7月末@ナイロビ)に判断を先送る形となりました。
議題7:遺伝子組換え生物(LMO)のリスクアセスメント
本議題では、カルタヘナ議定書の対象である遺伝子組換え生物(LMO)に関するリスクアセスメント・リスク管理の指針をどのように更新するかが議論されました。特に、微生物・魚類・遺伝子ドライブ等の新しいタイプのLMOが増えつつある中、従来型の指針のみでは十分に対応できない可能性が指摘されており、追加のガイダンス開発や能力構築をどの程度進めるかが焦点となった形です
成果文書のポイント(何を決めたか)ほとんど[ ]非同意事項となりました、
- 特定トピックに関する新たなガイダンスを最大2件まで開発する方針が議論された(例:微生物、魚類、遺伝子編集を利用した害虫制御等)。
- 能力構築の拡充(研修、オンライン情報共有、事例収集)を推進する策
- 専門家会合(AHTEG)再設置と、オンラインフォーラムの継続
- 各国に対し、リスク評価に関するデータ・経験の提出
などが、CPO17で検討されることが予想されます。
議題8:外来侵入種(Target 6:侵略的外来種の管理)
生態系劣化や農林水産被害を引き起こす外来種は、KM-GBFの中でも優先度の高い課題の一つであり、とりわけ島しょ国、途上国、地域共同体が高い影響を受けています。本議題では、侵入経路の把握、データ整備、監視・早期発見・迅速対応(EADR)の強化、部門横断の協力体制の確立が鍵であることが確認されました。また、国境を越える対応の必要性から、政府・自治体・民間部門・先住民・地域住民の連携が重要である点が共有された。
成果文書のポイント(何を決めたか)
各国に対し、
- 侵入経路・影響・分布に関するデータ収集・共有の強化を奨励。
- 貿易・観賞生物・輸送・オンライン取引など、新たに拡大するリスク経路にも対応するよう呼びかけ。
- 部門横断・国境を越える協力を強化することを奨励(農業、観光、港湾、都市管理など)。
事務局に対し、(財源が確保された場合)
- eDNA や AI を含む新しい検知技術の研修教材の作成、外来種ポータルの拡充(多言語化・国別リスト掲載)オンラインフォーラムの開催、などを要請する案をまとめました(が非合意事項となりました)
議題9:農業と生物多様性(特に土壌生物多様性)
本議題では、土壌生物多様性が食料安全保障、土地劣化の防止、気候変動緩和、生態系回復に果たす中心的な役割が再確認された。特に、菌類(Fungal Biodiversity)の知識と政策上の認識が著しく不足していることが、国家政策や研究体制のギャップとして明確に指摘された。農業政策を「生産性中心」から、「土壌生態系の機能と健全性を基盤とする体系」に転換する必要性が議論の中心となった。加えて、先住民・地域共同体(IPLC)、女性、農民、若者の知識と参加が、土壌管理の実効性に不可欠である点が強調された。
成果文書のポイント(何を決めたか)
国とFAOに対し、「土壌生物多様性国際イニシアチブ(2020–2030)」の行動計画の実施を継続し、障害を整理しつつ改善を図るよう奨励。
各国は、土壌生物多様性の保全・回復・持続利用を、NBSAP(国家生物多様性戦略)および農業・土地・気候政策に統合することが促された。
農業・環境・保健分野の省庁横断調整メカニズムの設置を検討することを推奨。
有害補助金の転換(生物多様性に悪影響を与える補助金の削減・再配分)が明確に言及された点は今回の重要な進展。
先進国および支援能力のある国に対し、途上国への資金・能力構築・技術移転の支援を強化することを要請。
土壌生物多様性モニタリング手法の国際的な整合・データの相互運用性の確保を、FAO・IUCN・GSBI等と協働して進めることが求められた。
議題10:生物多様性と健康
本議題については、関係機関による指標、測り方(Metrics)、測定手法の進展に注目しつつ、生物多様性と人の健康の相互依存関係を政策に統合するための手法が議論されました。健康は生態系サービスを通して支えられており、また生物多様性の劣化は感染症リスクや栄養不良、精神的健康への影響を含む多様な形で人々の暮らしに波及します。
SBSTTA27では、健康分野と自然保全分野を分けずに統合的に取り組む「One Health アプローチ」と、各国の政策における生物多様性と健康の主流化が中心テーマとなりました。
成果文書のポイント(何を決めたか)
事務局に対し、生物多様性と健康に関連する指標・測定手法の整理と開発スケジュールの調整を要請(レビューのための時間確保を明記)。
第17回締約国会議(COP17)向けに、指標案・事例・実施状況の進捗報告を提出することを事務局に求めた。
各国に対し、生物多様性と健康の関係性を国家生物多様性戦略(NBSAP)および保健政策に統合することを奨励(非合意)
途上国支援のため、資金・能力構築・技術協力の拡充や、様々な事務局への要請事項も書かれていますが、非合意事項としてまとまりませんでした。
国際自然保護連合日本委員会 道家哲平