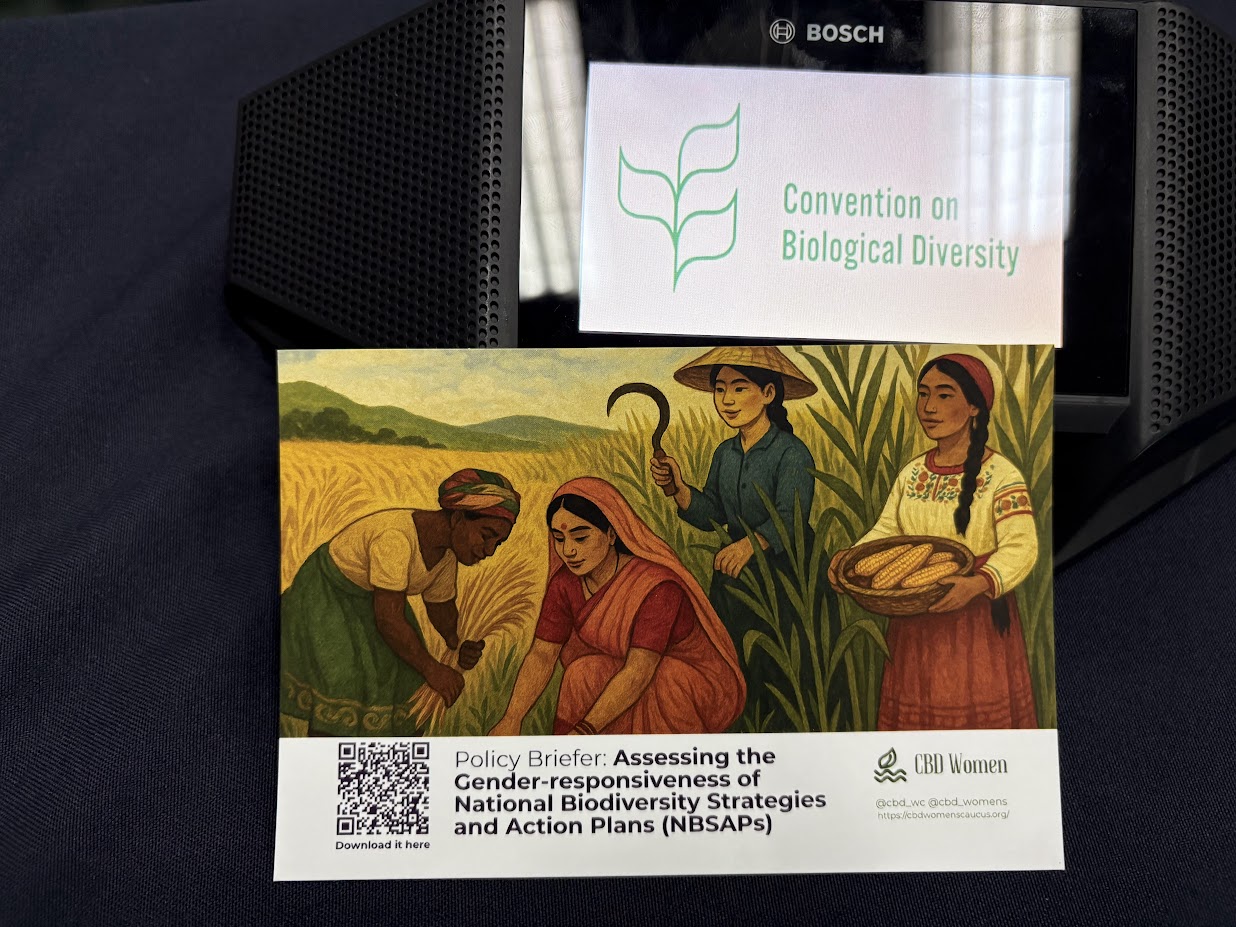10月22日、第27回科学技術助言補助機関会合の二日目になります。
午前の本会議では気候変動の議題を扱い、午後ではKMGBF実施のための科学技術的ニーズという議題への意見だしが行われました。気候変動は、COP16決定に基づいて、生物多様性条約と気候変動枠組み条約との連携模索を行う中で、自然に根差した解決策または生態系ベースアプローチに関する自発的ガイダンスを含むこの領域で取り組むべき活動を議論するものです。自発的ガイダンスは、検証の時間が足りないとして、SBSTTA27で意見を出し、COP17までに更新・ピアレビューを実施して内容を高めたいとの意見があり、引き続き議論というよりは意見出しが中心になりそうです。
午後は、COP15から16の間に行われた新しい世界枠組みを実施するために既存の作業で見直すべきこと、その一つとしての森林作業計画の更新、新たに取り組むべきプログラムの検討という3つのサブ議題を持っています。この議題後、カルタヘナ議定書に関係の深い議題を扱いました。締約国から出された「今後作成が優先される遺伝子組み換え技術・活用方法」を元に専門家会合が4つの技術の自発的ガイダンス、3つの技術ノート開発の必要性を提案し、新たな専門家会合の設立も提起しています。この提案を協議しました。意見としては、「4つのガイダンスや3つのノート開発の必要性や実現可能性」「新たな専門家会合の是非」などが意見として分かれていたように思います。また、途上国からは能力開発や技術移転の重要性を指摘する声が多くありました。外来種に関する議題の意見出しも終わらせました。全体進行としては予定よりも遅れており、NGO含む、オブザーバーが一切発言できない進行になっています。
午後の課題を詳しく考えるためサイドイベントに参加しましたので、その報告をします。
CBD生物多様性条約のプログラムを再設計へ― KMGBFに沿った整理と新たな課題領域の検討 ―
「Strategic review and analysis of programmes of work under the Convention in the context of KMGBF」というタイトルで、生物多様性条約事務局が主催したサイドイベントに参加しました。生物多様性条約第27回科学技術助言補助機関会合(SBSTTA27)では、クンミン・モントリオール生物多様性枠組(KMGBF)の採択を受けて、条約が抱える多数の作業計画(Programme of Work, PoW)をどのように整理・再構築するかが主要な議題となりました。本サイドイベントでは、事務局による包括的なレビュー結果の報告に加え、今後新たに検討すべきプログラム領域の方向性、そして実際にPoWを活用して国内政策を展開している事例の共有が行われました。
既存プログラムのレビューと整理
CBDではこれまで30以上の作業プログラムを抱え、森林、島嶼、保護地域、気候変動など多岐にわたるテーマで行動計画が存在します。しかし、会議では「すべての作業プログラムがKMGBFの実施に直接貢献する形へ整理すべき」との方針が共有されたことを受け、事務局はKMGBFとの整合性、CBDが主導すべき役割、これまでの経緯などの基準で評価を行いました。
結果は三つのカテゴリーに整理されました。
- 維持すべき分野(Minimal adjustment):農業・森林・沿岸海洋・保護地域など、既に明確な目的を持つ領域。
- 再検討を要する分野(Further consideration):ABS(アクセスと利益配分)や企業参画、回復、生態系アプローチなど、他の条約・機関との連携を深める余地のある領域。
- 効率化の余地がある分野(Opportunities for efficiency):乾燥地、山岳地域、生物文化多様性など、CBD以外のプロセスで扱う可能性がある領域。
レビューの背景には、COPごとに新たな決定が積み重なり、結果的に条約の作業量が増大している現状があります。今後は、重複を避け、限られた資源を重点的に活用するための再設計が求められています。
新たに検討すべき5つの課題領域
SBSTTA25・26では、既存の1,200を超えるガイダンスやツールを精査し、GBFの実施と既存のツールの間でギャップのある5つの分野が特定されました。
- 空間計画と生物多様性:IPBESで評価が進行中であり、保護地域の配置や土地利用計画との統合が鍵となります。
- 汚染と生物多様性:関係者が多く、条約上でも注目されているが、実践的なガイダンス整備が遅れており、今後の検証が必要
- 持続可能な生物資源利用とサービス
- ジェンダー・人権ベースアプローチ・公正な利用
- 多様な価値体系の統合
これらに対して、どう取り組み出来そうかを事務局で案をまとめ、SBSTTA27で方向性を合意する予定です。
各国からの作業プログラムの活用事例
発表では、アラブ首長国連邦(UAE)とバングラデシュが、それぞれの作業プログラム(PoW:Programme of Work)をもとにした国内実施事例を紹介しました。
UAEは「海洋・沿岸のPoW」を翻訳する形で国家戦略を展開し、サンゴ礁やマングローブの再生、保護地域の拡大、KBA(重要生物多様性地域)の特定などを実施。劣化したマングローブ林の20%を再生し、インドネシアとともに「マングローブ・アライアンス」を設立しました。
バングラデシュでは「森林のPoW」を基盤に、コミュニティ参加型の森林管理を推進。森林法や野生生物法の整備、知識共有や利益配分制度の導入を進め、成功事例を蓄積しました。一方で、土地利用の競合や気候変動によるリスクが依然として課題となっています。

質疑と今後への視点
議論では、バイオエコノミーの新プログラム化について質問ができました。パネリストからは「バイオテクノロジーや地域経済循環、持続可能な資源利用など、国ごとにとらえ方(定義)が多様であるため、まず原則と共通理解を整理することが重要」との回答が出されました。
元CBD事務局長のブラウリオ・ディアス氏は次のように問いかけました。
「私たちは今、極めて意欲的な世界目標の実現に残り5年しかない。この限られた時間を、既存プログラムの再検討に費やすのか、それとも実践的な行動強化に向けて投資するのか。最も効果的なリソースの使い方は何かを見極めるべきだ。」
この言葉は、CBDの全体運営における根本的な問いでもあります。KMGBF実施に向けた「制度の整理」と「現場での実践推進」をどう両立させるか――その舵取りこそ、今後の会議で問われる核心といえるでしょう。
国際自然保護連合日本委員会 道家哲平