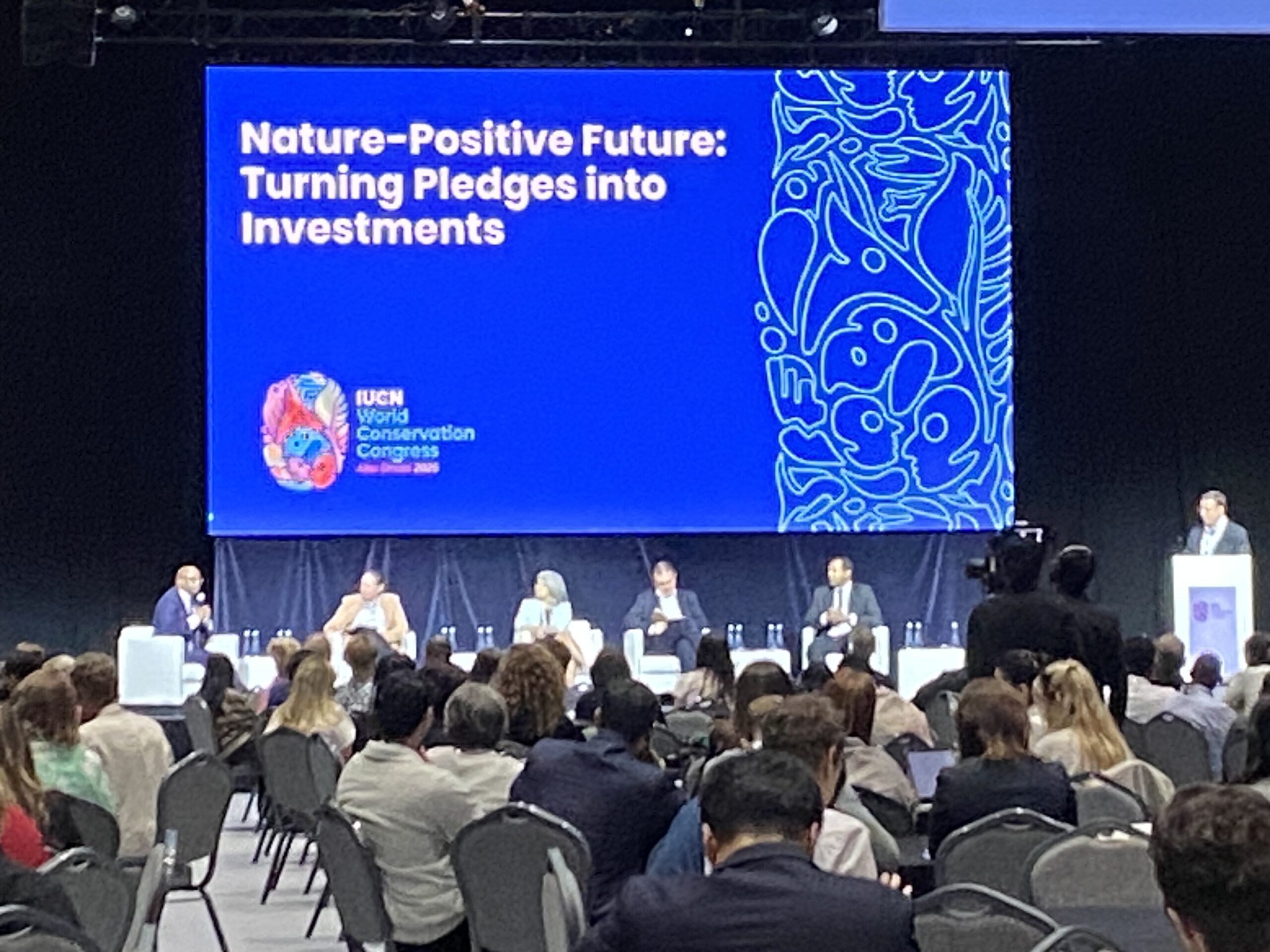「Decent work in Nature-based Solutions: Unlocking jobs through investment in nature and conservation(自然に根ざした解決策で“働きがいのある雇用”をひらく)」セッションに参加しました。生物多様性と経済をどう結び直すか。教育・スキル、投資、政策、そして“仕事の質”まで踏み込んだ議論から、自然に根差した解決策(NbS)がもたらすチャンスと課題が見えてきました。
なぜ今、NbS×雇用か
冒頭、キーノートスピーチを務めたCBD事務局長のアストリッド・ショーマカー氏は、「気候でも雇用の議論が中心になっている。同じように自然にも大きなポテンシャルがある」と強調。「経済活動が自然を破壊しないように設計し、自然に恩恵を“払い戻す”発想へ」というメッセージが会場に響きました。NbS(Nature-based Solutions)は、コストに対して8~9倍の社会的・経済的リターンが見込めると紹介され、教育システムや知識共有、スキル育成のあり方に波及効果をもたらす点も示されました。レンジャー等の現場職の重要性・役割拡大にも言及があり、ILO×UNEP×IUCNの連携で“グリーントランジションにおける雇用”を具体化していく方向性が示されました。
共同報告のポイント(IUCN/ILO/UNEP)
IUCNのJuha氏からは、2022年・2024年の共同報告のアップデートが共有されました。内容面の分担としては、ILO=ディーセント・ワーク、UNEP=ファイナンス、IUCN=自然保護の知見をそれぞれ専門機関の立場から貢献しあったそうです。報告の柱は、NbS関連雇用の現状と将来可能性、仕事の質の評価、主要課題への対策、より一貫性ある政策・戦略の提案でした。
現状のNbS雇用はパートタイム・季節労働・農山村地域中心の色合いが強く、「分類や定義の未整備」「測定指標の不足(“働きがい”の定義を含む)」「ボランティア依存による実態の見えにくさ」といった測定と可視化の壁が課題として指摘されました。
数字でみる雇用創出ポテンシャルについては、現在:約6,000万人がNbS関連で従事(推計)しているとみられる中、2030年までに:2,000〜3,100万人の純増の可能性があると報告書では指摘します。地域別の見立てでは、アジア太平洋が最も大きく、アフリカ、EUも続く形で増加見込み。アジアでは約1,100〜1,600万人の追加雇用が見込まれるとの紹介がありました。※いずれもセッション時点の推計レンジ紹介。定義や統計の整合に依存するため、今後の指標整備がカギになります。

現場のリアリティ:ケニアの例
ケニアでは「150億本の森林再生」を掲げ、レンジャーを5倍に増やさないと自然を守り切れない、という切実な現場感が共有されました。必要なのは生態系の知識+ステークホルダーマネジメント+インフラ整備+コミュニティ連携まで、複合的なスキルが求められています。
政策・実装への提言として、下記が指摘されています
- スキル開発投資:教育カリキュラムと職業訓練をNbS時代に最適化
- 権利と包摂:転換期の労働者の権利保護と、女性・若者・先住民などの参画促進
- データと指標整備:セクター定義、職種分類、“働きがい”の評価枠組みの共通化とオープン化
グリーントランジションの眼差し
コメントに立ったヴァレリー・ヒッキー氏は、「移行の中で起きる雇用の“変化”を丹念に捉えること」の重要性を強調。数を増やすことと同時に、仕事の質(安全・公正・生計の安定・キャリアの見通し)をどう担保するかが、NbSの持続可能性を左右すると指摘しました。自然保護に関わる人々の当事者意識を高める設計(人事制度、評価、誇りを育む仕掛け)も鍵になります。
日本への示唆(私見)
- 地域創生×NbS雇用:里地里山、沿岸・河川、都市のグリーンインフラなど、日本の強みと雇用創出を直結させる。
- “測れる仕組み”を共通化:企業・自治体・NPOの成果を比較可能に。教育・研修の連携もスケールへ直結。
- 自然保護ボランティア・レンジャー職の再定義:様々な保全活動従事者が持っているスキルを可視化し、保全活動ごとの標準作業量などを明確化することで、保全・監視に限らず、モニタリング、来訪者対応、地域合意形成を含むマルチスキル職として魅力を高める。
- 金融との橋渡し:公共投資・企業投資・市民出資を束ね、安定雇用につながる収益設計(長期契約、成果連動、自然資本の価値化)を拡充。
まとめ
NbSは自然を守りながら雇用を生む。ただし「測れないものは拡大しにくい」。日本においても、指標整備とスキル投資、包摂的な人材育成で、現場の仕事を“誇れるキャリア”へ—その道筋を考えていくことが大事であると思いました。
国際自然保護連合日本委員会 道家哲平