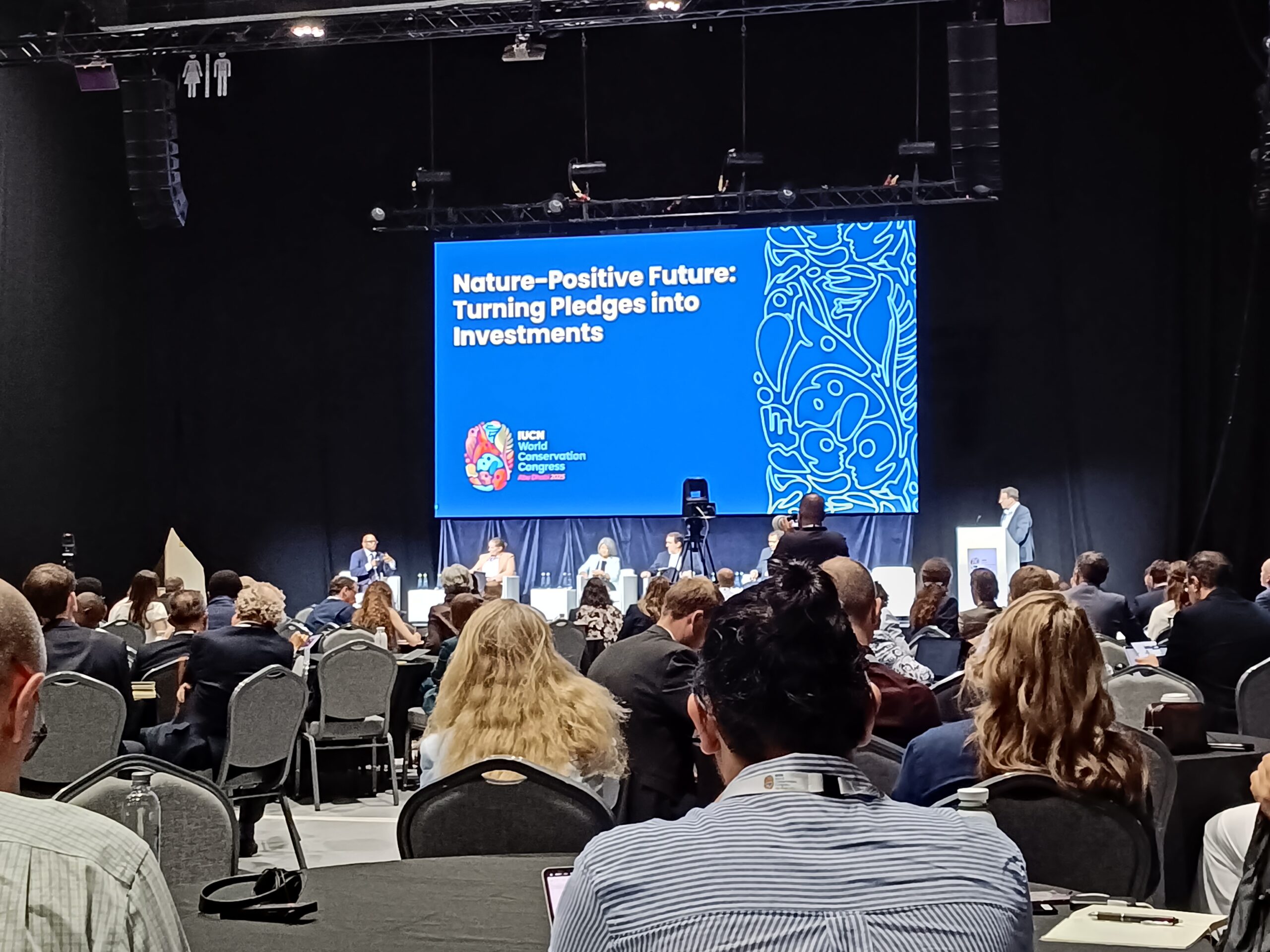日本自然保護協会の森本優花です。「Nature is everyone’s business: Mobilising Capital for Biodiversity and Resilience」というイベントに参加しました。このイベントでは、生物多様性資金のギャップを埋めるうえで重要な役割を果たす民間セクターの可能性に焦点が当てられました。金融機関、企業、NPOの代表者が登壇し、より効果的な自然資本やの資金動員やパートナーシップを実現するための成功事例、学び、課題、そして今後の機会について共有しました。
BNPパリバ銀行(金融セクター)
テーマ:自然保護を中核に据えた持続可能な金融戦略
BNPパリバのフローレンス氏は、同社のサステナビリティ戦略において「自然保護(生物多様性)」をエネルギー転換と並ぶ最優先課題として位置づけていると述べました。同社は2035年までに自然関連取引へ40億ユーロを供給する目標を掲げていましたが、2024年末時点で既に54億ユーロを達成し、目標を上回る成果を上げています。具体的な取組として、ウルグアイ政府向けインパクト主権債では保護林面積を成果指標(KPI)の設定や、ラテンアメリカ沿岸の保全を目的とした1億3,000万ユーロ規模のブルーボンドを発行。また、海洋保護区の強化を支援する信用制度や、生物多様性モニタリング技術を開発するスタートアップへの投資も進めています。フローレンス氏は、「自然保護分野における資金循環を生み出す新しいビジネスモデルを構築したい」と述べ、金融の力による持続的な自然保護の実現を強調しました。一方で、自然保護に関わる金融には「不確実性」という課題があると指摘しました。自然には明確な価格がついていないため、投資家がビジネスモデルを構築しづらい現状があります。投資家は予測できないリスクを避ける傾向があるため、これが資金の流れを妨げる要因になっていると説明しました。この課題に対応するため、TNFD※1、PBAF※2、ICC※3等の国際的な枠組みが、自然リスクの評価や価格づけの仕組みを整備しつつあります。また、欧州中央銀行(ECB)が銀行に対し、自然関連リスクを財務リスクとして評価するよう求めていることにも言及し、「このような流れが、自然に価値をつける流れをさらに加速させるだろう」との見解を示しました。
※1 TNFD:Taskforce on Nature-related Financial Disclosures(自然関連財務情報開示タスクフォース)
※2 PBAF:Partnership for Biodiversity Accounting Financials(金融向け生物多様性会計パートナーシップ)
※3 ICC:International Chamber of Commerce(国際商業会議所)
王子ホールディングス(企業)
テーマ:森林の価値を高めるための取り組み
王子ホールディングスの鎌田氏は、主に「製品開発」と「自然資本の評価」の2つの分野で活動を進めていると述べました。まず、製品開発では、森林資源から新たな価値を生み出す研究を進めています。主力製品である紙に加え、森林由来のエタノールを活用し、持続可能な航空燃料(SAF)や医薬品原料としての利用を目指しています。次に、自然資本の評価については、学術機関と連携し、自社の森林にカメラや録音装置を設置して生物多様性をモニタリングしていると説明しました。こうしたデータをもとに「自然の貸借対照表」を作成し、森林全体の価値を数値として可視化することを目指しています。鎌田氏は、これらの取り組みを通じて「生物多様性と利益の両立」を実現し、持続可能な社会づくりに貢献していきたいと締めくくりました。
ブルーカーボンプロジェクト(NPO)
テーマ:地域とともに進める沿岸生態系の保全
ブルーカーボンプロジェクトのカミル氏は、フィリピン全土の沿岸生態系を保護する取り組みについて紹介しました。このプログラムは2020年に開始され、放棄された養魚池のマングローブ再植林だけでなく、地域社会の生計支援も取り組み、「自然保全」と「地域経済」を両立させるモデルへと発展。現在は、地域住民と協力して漁業などの新たなビジネスを立ち上げ、保全活動と収入機会の両立を図っています。また、このプログラムでは地域住民を雇用し、マングローブや海草、微生物などのデータを収集しています。自然資本会計の制度が十分に整っていないフィリピンにおいて、こうした科学的データは極めて重要であり、企業の支援を受けながら持続的な雇用とモニタリングの仕組みを確立していると述べました。カミル氏は、地域の人々が自ら自然を測り、守る主体となるこの取り組みは、社会的にも公正であり、企業にとっても「成果を可視化できる持続可能なモデル」であると強調しました。
まとめ
最後にBNPパリバ銀行は、自然保護に関する資源動員を加速させるためには、科学者の関与とデータに基づく判断が重要性だと強調しました。正確な科学的根拠に基づくことで、意図しない負の影響を避けることができると述べました。また、地域住民を初期段階から参画させることが不可欠であり、多くのカーボンクレジット事業で地域に利益が還元されていない現状は「不公正であり、正しいやり方ではない」と指摘しました。その実践例として、BNPパリバ銀行ではアマゾン地域で先住民主導の森林保全プロジェクトを開始しています。 3名の登壇者からは、自然保護投資は「コスト」ではなく「価値創造」であることが繰り返し示されました。そして、自然を守るには、地域社会をパートナーとして巻き込むことが不可欠であるとの意見が協調されていました。
コメント
金融セクター、企業、NPOが地域の自然保護に取り組む際に、地域社会が主体的に関わることで、プロジェクトはより持続可能なものとなり、結果として地域の自然に基づく解決策(NbS)にもつながるという考えが共通の認識されていました。日本自然保護協会が自治体や企業と連携し、地域ごとのネイチャーポジティブを目指して進めている「日本版ネイチャーポジティブアプローチhttps://www.nacsj.or.jp/activities/project/npa/」の方向性は、国際的な潮流と一致しているとの確信を得ることができました。また、フィリピンの取り組みでは、地域住民自身が自然データを収集する仕組みの重要性も指摘されています。日本自然保護協会では、誰もが活用できる自然の状態を測る評価手法の開発を進めています。地域の保全活動を担う人々が自分たちでモニタリング調査が可能となるよう、取り組みを進めていきたいと思います。
自然保護の取り組みを実現・拡大するためには、金融セクターとの連携が欠かせません。セッションでは、金融機関が企業と協働し、地域に根ざした自然保護活動を支援している事例が多数紹介されました。日本自然保護協会も環境NGOとして、金融機関との協働を一層強化していく必要性を再認識しました。
日本自然保護協会 森本優花
登壇者
- Ms. Razan AL MUBARAK IUCN
- Mr Humphrey KARIUKI Janus Continental Group
- Mrs. Laurence PESSEZ BNP Paribas
- Mr Kazuhiko KAMADA Oji Holdings Corporation
- Ms. Frances Camille RIVERA Oceanus Conservation