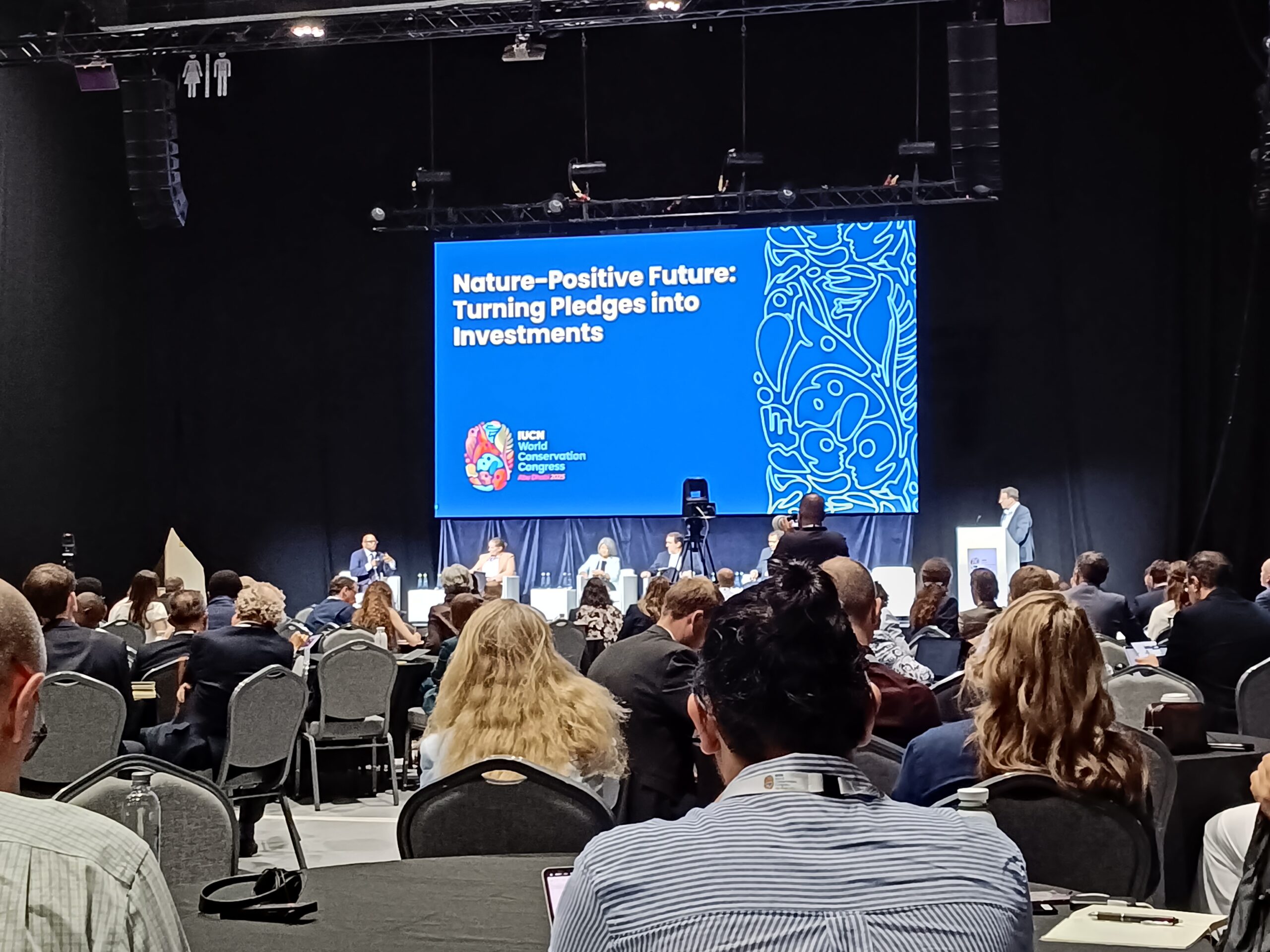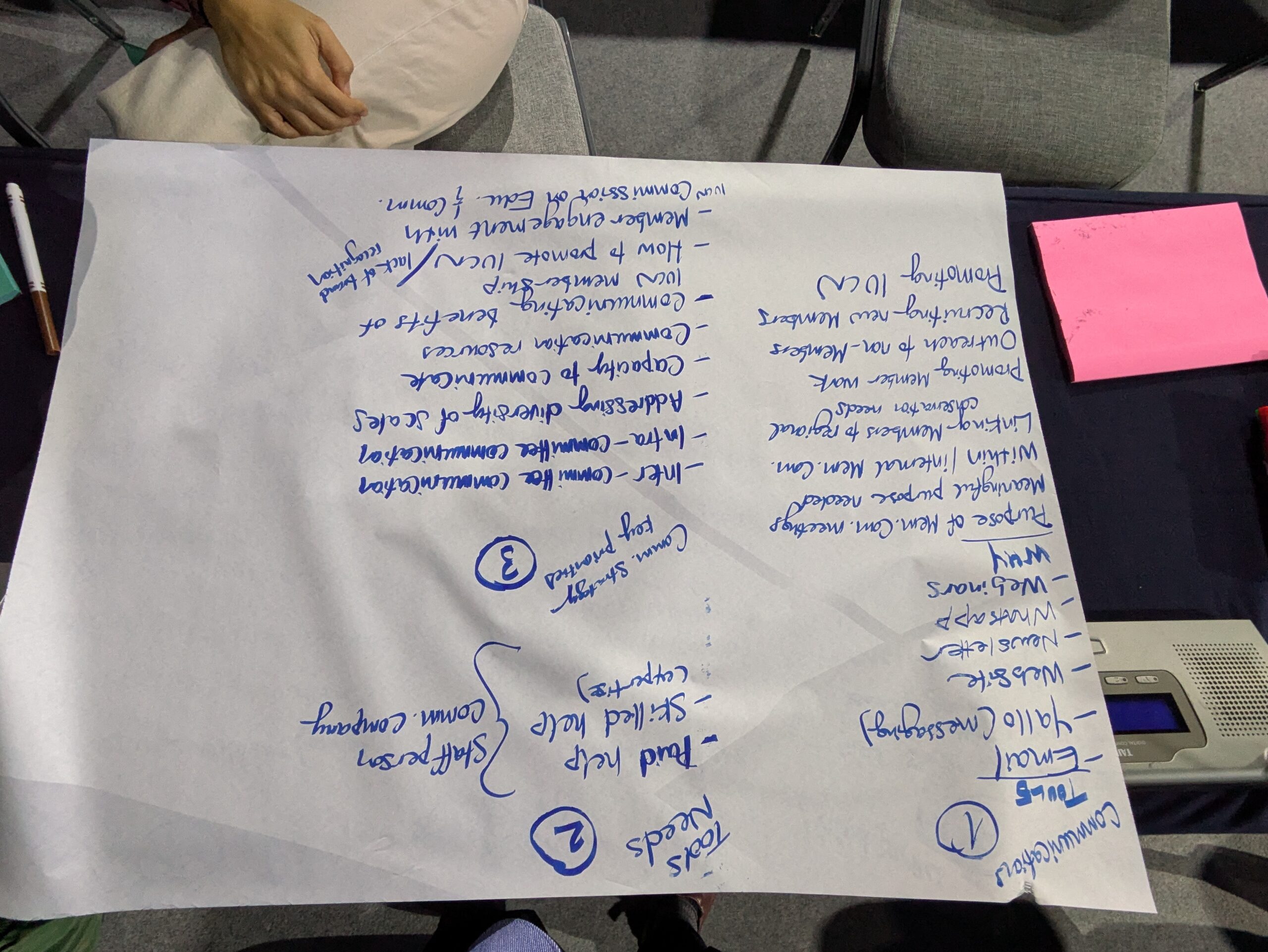― IUCN WCC 2025 Asia Pavilionセッションを踏まえて ―
1.背景:OECMとNature Positiveの新たな関係性
近年、世界的な生物多様性保全の潮流の中で注目されているのが、OECM(Other Effective area-based Conservation Measures)とNature Positiveという二つの概念である。
OECMは、法的な保護区に限定されずとも、結果として長期的に生物多様性保全に貢献している地域を認定する仕組みであり、昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)のターゲット3(30by30)の実現における重要な柱の一つである。
一方、Nature Positiveは「2030年までに自然損失を止め、回復軌道に乗せる」という国際的目標を掲げ、社会全体の構造転換を促す包括的ビジョンである。
両者はスケールも起点も異なるように見えるが、共通して「生物多様性の主流化」と「多主体協働による社会変革」を核に据えている。
2.アジア地域におけるOECMの進展と課題
アジアパビリオン・セッション「Progress and Challenges toward Achieving the Target 3 of the GBF in Asia」では、日本、マレーシア、IUCNアジア地域事務所などによるOECMの実践事例と課題が報告された。
日本では「30by30ロードマップ」に基づき、政府・企業・NGO・地域住民が連携する国家認定制度が進行中である。企業が所有する森林やダム湖周辺の生態系をOECMとして登録し、保全成果を国の進捗指標に反映するなど、官民協働による科学的データに基づいた可視化が進む。
一方、マレーシアでは、地域住民・政府・NGOが共同で評価する参加型プロセスが導入され、OECMが「地域社会の自発的保全」を体現する制度として機能している。
IUCNアジア地域事務所は現在、各国間の定義や評価手法の調和を進め、グリーンリスト制度を通じたOECMの国際的比較と資金動員の基盤整備を進めている。
しかし、アジアに共通する課題として、資金・人材・データ不足が依然として大きい。特に地域社会主体のOECMは長期的支援を欠くと脆弱化しやすく、継続的モニタリングと制度的安定性の確保が求められている。
3.Nature Positiveの理念とグローバルな潮流
Nature Positiveは、単なる「自然損失の抑制」ではなく、自然資本を回復させる社会経済モデルへの転換を意味する概念である。これは、2022年の昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)で掲げられた「2030年までに自然損失を止め、回復軌道に乗せる」という目標を具体化するための中核的なビジョンでもある。
「Nature Positive Action on the Road to COP17」と題したセッションをはじめ、複数の議論において、政府・企業・金融機関・市民社会など多様な主体が連携し、経済・社会の構造転換を通じて生物多様性の回復を実現する必要性が強調された。特に、企業セクターでは、自然への投資を「コスト」ではなく「価値創造」として再定義する動きが進んでいる。
こうした世界的潮流は、地域スケールでのOECM実践と接続することで、理念(Nature Positive)から実践(OECM)への橋渡しを可能にする。すなわち、グローバルな政策目標が地域社会で具体的な行動として具現化されるプロセスこそが、真に「Nature Positiveな社会」への転換を支える鍵となる。
4.両者のシナジー:ローカル・トゥ・グローバルの架け橋
OECMとNature Positiveは、目的とスケールの異なる二つのアプローチでありながら、「地域スケールの実践」から「地球スケールの転換」へという共通の構造をもつ。
OECMは、地域での多様な取り組みを可視化し、それらを国際的指標に統合する仕組みである。各地域の努力の積み重ねが、Nature Positiveというグローバル目標の実質的な達成を支える「現場の基盤」となる。
また、OECMで収集された科学的データやモニタリング情報は、Nature Positiveの進捗評価に資する重要な基礎情報となる。
さらに、両者に共通する理念は「包摂性」と「伝統知の尊重」である。アジア地域では、先住民や地域社会が守ってきた森・里山・マングローブがOECMとして評価されつつあり、それらの文化的価値がNature Positiveの文脈の中で再認識されている。
つまり、OECMは地域の知と文化を通じてNature Positiveの倫理的基盤を具現化していると言える。
5.熊本サミットと今後の展望 ― アジア発の自然再興モデルへ

2026年7月、熊本で開催される第2回グローバルネイチャーポジティブサミットは、COP17に向けた中間評価の要となる。
このサミットは、企業や自治体の貢献を可視化し、社会全体での自然再興を推進する場として位置づけられており、日本がOECMとNature Positiveの双方を融合的に推進することが期待されている。
熊本は、阿蘇の草原や地下水涵養システムなど、自然と人の共生を実現してきた地域であり、その経験自体が「ローカル・トゥ・グローバル」の好例である。
この地での議論は、アジア地域全体の自然再興型ガバナンスに向けた指針を提示する契機となるだろう。
6.結論:OECM×Nature Positive=未来のガバナンスモデル
OECMは「地域での実践的基盤」、Nature Positiveは「社会全体の方向性」。
この二つが有機的に結びつくことで、科学・政策・経済・文化を横断する多層的な自然共生社会モデルが構築される。
アジアの多様な文化と生態系のもとで育まれたOECMの経験は、Nature Positiveにおける最前線であり、日本が科学的知見・政策設計・ユース参画を通じてその連携を深化させることは、COP17に向けた国際的リーダーシップの発揮にもつながるだろう。
両者の結合は、単なる環境政策ではなく、「自然と人間社会の新しい関係性」を再構築する社会契約である。
OECMが示す現場の力と、Nature Positiveが掲げるグローバルビジョン。
それらが交わる点にこそ、アジアから世界へと広がる“自然再興の未来地図”が描かれつつある。
Japan Youth Platform for Sustainability (JYPS) 嶋田恭子