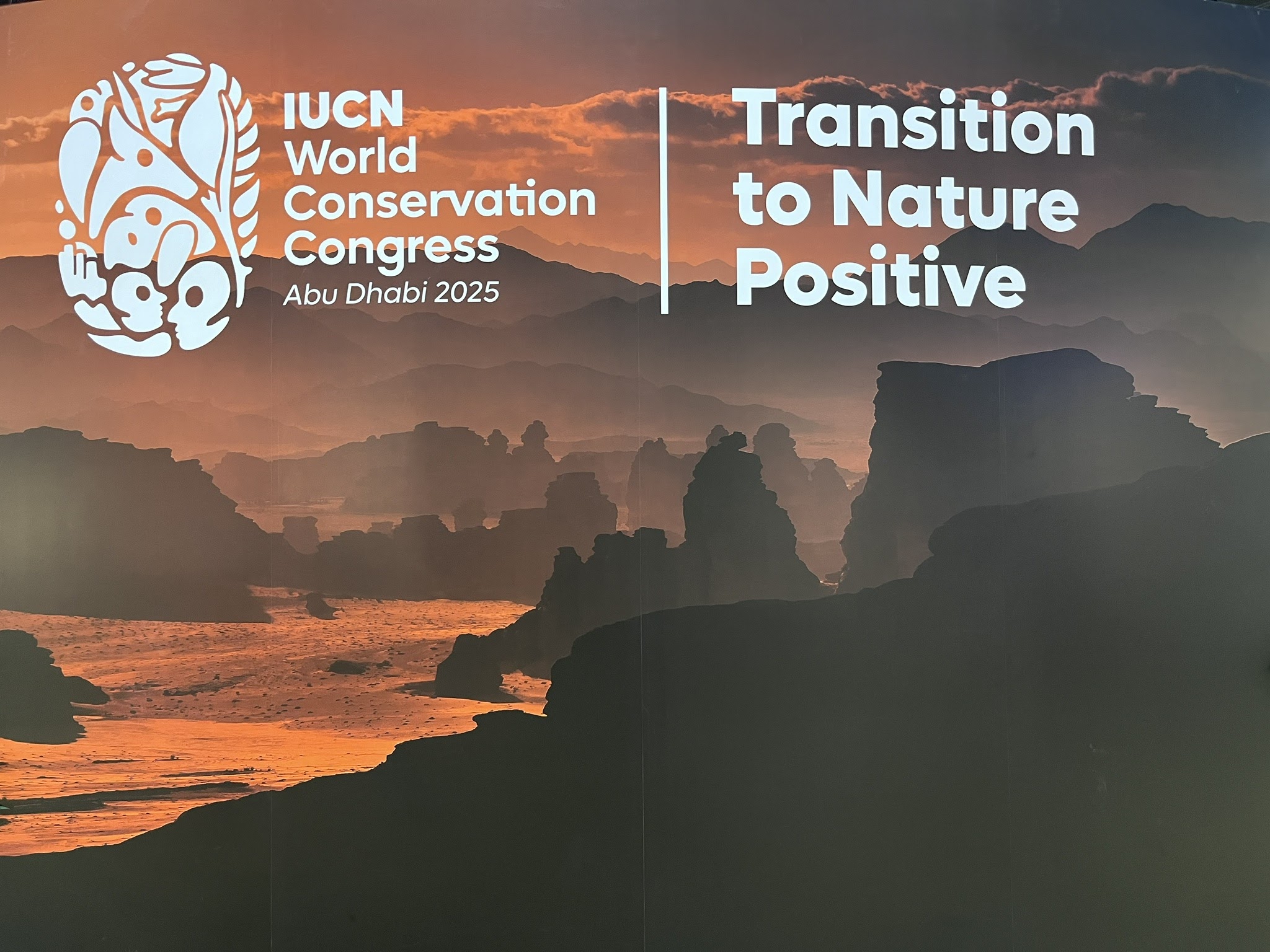1 はじめに
今回のブログでは10月12日、IUCN-WCC国際会議で行われた草原・干旱地域に関するセッションの内容をまとめてみました。このセッションでは、モンゴル館の高官や国際機関の専門家が集まり、草原・干旱地域における生態系保全や土地管理の現状、課題、そして政策的・国際的な取り組みについて語り合っていました。
特に、地域住民への影響や生物多様性保全、国際協力の重要性が大きなテーマでした。発表やパネルディスカッションを通して、私自身も多くの学びを得ることができました。本ブログでは、講演内容の整理、パネルディスカッションの内容、そして私の個人的な感想をまとめます。
2 H.E. Batbaatar Bat氏による草原・干旱地域に関する講演
セッションはChetan Kumar氏(Global Head, Forest and Grasslands, IUCN)が司会を務め、まずH.E. Batbaatar Bat氏(Minister of Environment and Climate Change, Mongolia)が講演を行いました。主な内容は以下の通りです。
- 草原・干旱地域の現状
モンゴルの広大な草原や干旱地域では、過放牧や気候変動により土地劣化が進行しており、砂塵嵐の頻度が増加していることが報告されました。これにより、地域住民の生活や牧畜生産に直接的な影響が出ていることが強調されました。 - 生物多様性保全の必要性
草原・干旱地域には多様な野生動物が生息しており、絶滅危惧種も含まれます。Batbaatar氏は、これらの生息地を守ることが国際的な責務であると述べ、政策的支援と地域参加型保全の重要性を示しました。 - 政策・国際協力の重要性
国内での施策に加えて、UNCCDやIUCNなど国際機関との連携が不可欠であることを強調しました。また、COP17をモンゴルで開催する予定であることを紹介し、国際的な議論を通じて草原・干旱地域の保全・管理の重要性を世界に発信する意義を述べました。科学的データや技術支援を活用することで、効果的な土地管理・回復が可能になると述べました。
3 パネルディスカッション:持続可能な草原・干旱地域管理

パネリスト:Andrea Meza Murillo氏、Stéphanie Bouziges-Eschmann氏、Ahmad Al-Anazi氏、Houria Djoudi氏、Jean-Marc Sinnassamy氏
3.1 主な発言
- Andrea Meza Murillo氏
UNCCDとして、劣化地管理や国際協力の推進、政策支援の必要性を強調しました。特に、草原・干旱地域の回復は単なる環境保護だけでなく、地域住民の生活や生計にも直結していることを指摘しました。また、国際的なパートナーシップの重要性についても触れ、各国政府や地域専門家と連携することで、より効果的な土地管理戦略が可能になることを示しました。 - Stéphanie Bouziges-Eschmann氏
FFEMの資金提供事例を紹介し、地域レベルでのプロジェクト実施や効果的な監視・評価体制の構築の重要性を説明しました。特に、プロジェクト実施後のモニタリングを通じて、草原の植生回復や土地の持続可能な利用状況を定量的に評価することが、将来的な政策策定や資金配分に直結することを強調しました。 - Ahmad Al-Anazi氏
サウジアラビアにおける造林・緑化プロジェクトの経験を共有しました。現地専門家との協働、地域住民の参加、そして知見や成功事例の共有が、プロジェクトのスケーリングや長期的な持続可能性において重要であると述べました。また、劣化地回復における技術的課題や気候変動影響への対応策についても言及しました。 - Houria Djoudi氏
FAOの立場から、干旱地林業の管理手法や地域住民の参加型保全の重要性を解説しました。科学的データに基づく意思決定が、森林回復だけでなく、家畜管理や土壌保全など多面的な土地利用改善にもつながることを強調しました。また、地域住民との信頼関係構築がプロジェクト成功の鍵である点にも触れました。 - Jean-Marc Sinnassamy氏
GEFの立場から、資金提供や国際プロジェクトのサポートを通じた劣化地回復の取り組みを紹介しました。特に、資金提供だけでなく、技術支援や政策提言を組み合わせることで、プロジェクトの成果を最大化できることを説明しました。また、国際的な知見を地域に適用する際の課題や、現地条件に応じた柔軟なアプローチの重要性についても言及しました。
パネルディスカッションを通して、「異なる立場や専門性を持つ関係者が協力すれば、草原・干旱地域の持続可能な管理は現実的に可能であり、国際協力と地域参加がその成功の鍵である」と実感しました。特に、劣化地回復は単なる技術的課題ではなく、社会的・経済的要素も含む総合的な取り組みであることを強く感じました。
4 個人的所感
私は筑波大学のCPNC(Certificate Programme on Nature Conservation, University of Tsukuba)に参加しており、本プログラムではモンゴル国Hustai国立公園との協力プロジェクトもあります。今年の夏には草原調査の実習に参加する機会があり、草原の退化問題に関心を持っています。また、Hustai国立公園では絶滅危惧種であるTakhi(Przewalski’s horse, Equus ferus przewalskii)の保護活動も行われており、草原生態系と野生動植物保全の関係性を直接観察することができました。

今回のセッションに参加して、以下の点を特に感じました。
- 地域環境の現状理解の重要性
草原や干旱地域では土地劣化が進行しており、地域住民の生活や牧畜生産に直結する問題であることを改めて認識しました。現場の状況を直接観察した経験があるからこそ、講演内容の重要性をより実感しました。Takhiを含む野生動植物の生息環境が劣化すると、生態系全体への影響が広がることも理解しました。 - 多様な主体の協働
政府、国際機関、地域専門家の協働が不可欠であり、情報共有や科学的データの活用が課題解決の鍵となることが理解できました。草原調査実習でも、現地の関係者や研究者との協働が不可欠であることを学び、野生動植物保護の現場でも同様に多様な主体の協働が重要であることを実感しました。 - 実践経験から得た示唆
現場での調査経験を通じて、草原退化リスクや回復策の効果を評価することの重要性を実感しました。また、Takhiや他の野生動植物の保護活動に関する知見と今回のセッションで得た知識を組み合わせることで、持続可能な草原管理や生物多様性保全への貢献の可能性をさらに広げられると感じました。
セッションを通じて、「現場の課題は複雑だが、政策・科学・地域社会が連携すれば改善可能」ということを強く実感しました。将来的には、自身のCPNCでの経験や草原調査で得た知見を活かし、Takhiを含む野生動植物の保護と地域環境保全、持続可能な土地管理に貢献したいです。
5 結論
草原・干旱地域の持続可能な管理には、生態系保全と地域社会利益の両立が不可欠であり、政策支援や国際協力、地域専門家との協働が重要であることが確認できました。今後は科学的データに基づく計画策定、監視評価体制の整備、地域参加型プロジェクトの推進がさらに求められると感じました。
最後に、2026年にウランバートルで開催予定のUNCCD-COP17に参加し、草原・干旱地域の現状や課題、国際的な取り組みについてさらに学ぶとともに、自身の経験や知見を共有し、国際的な議論に貢献したいと考えています。
筑波大学 地球科学学位プログラム 修士1年生/
IUCN-Jインターン
SIQINGTUYA
登壇者一覧
- Chetan Kumar氏(Global Head, Forest and Grasslands, IUCN)
- H.E. Batbaatar Bat氏(Minister of Environment and Climate Change, Mongolia)
- Andrea Meza Murillo氏(Deputy Executive Secretary, UNCCD)
- Stéphanie Bouziges-Eschmann氏(Secretary General, FFEM)
- Ahmad Al-Anazi氏(Vice President, National Afforestation Programme, NCVC, Saudi Arabia)
- Houria Djoudi氏(Dryland Forestry Officer and COFC Dryland WG Secretary, FAO)
- Jean-Marc Sinnassamy氏(Senior Environmental Specialist, Global Environment Facility)