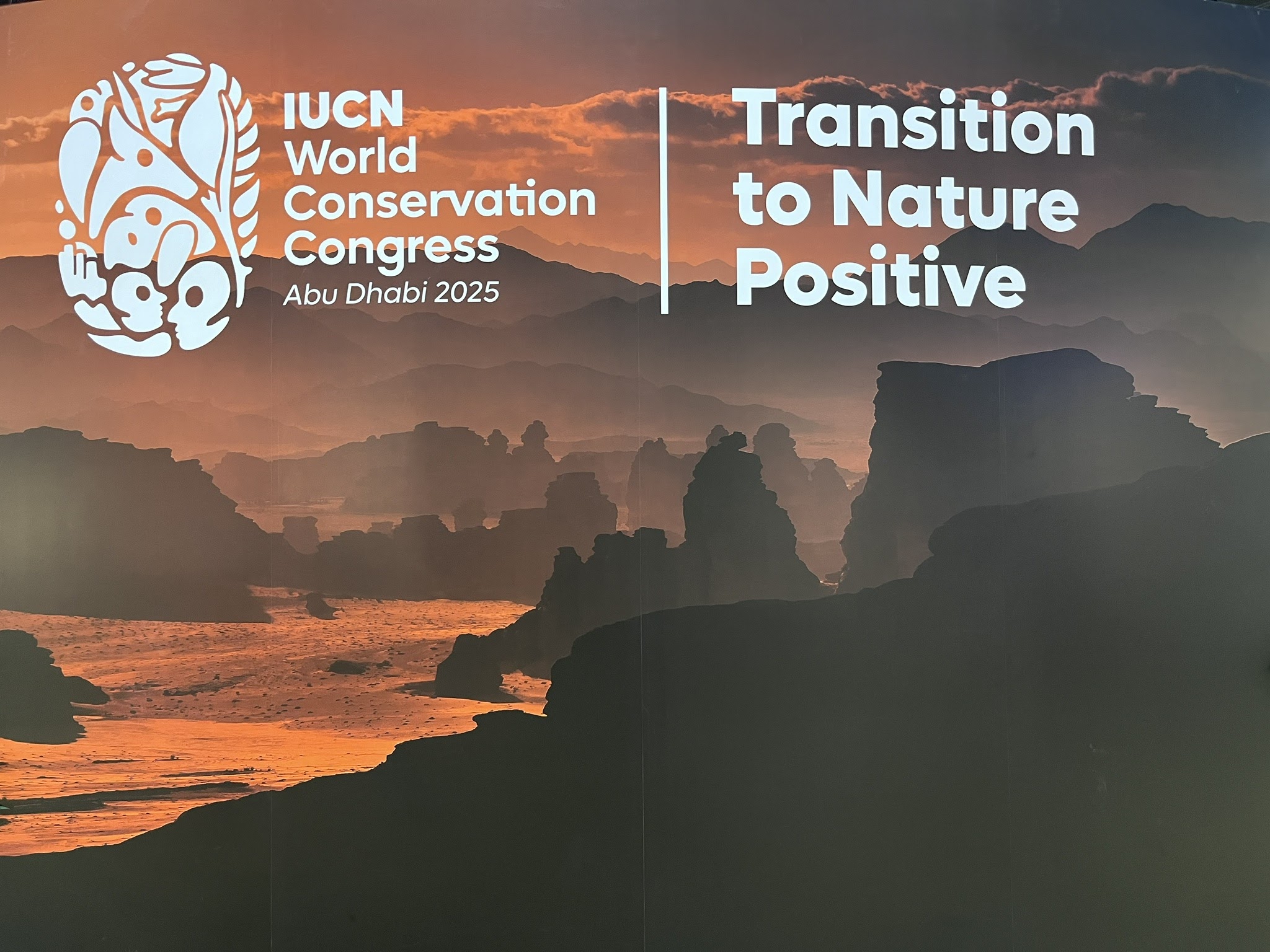アブダビで開かれたWCC(世界自然保護会議)で、私はBBC Studios Natural History Unit(NHU)のセッションに参加した。
世界の自然番組を牽引するBBCが「どのようにして“心を動かすストーリー”を生み出しているのか」、その現場の思考を垣間見る貴重な時間だった。
ストーリーとは、ヒーローと葛藤から始まる
スクリーンに映し出された最初のスライドには、こう書かれていた。
“Fundamentally, you need a HERO — a character to relate to.”
「本質的に、観客が感情移入できる“ヒーロー”が必要だ。」
物語には主人公がいて、課題があり、緊張と解決がある。
「もしドラマがなければ、それは退屈なポートレートにすぎない」と語るスピーカーの言葉は、動物ドキュメンタリーにも人間のドラマ構造が用いられていることを示していた。
彼らは“Classic Fairytale(古典的な物語構造)”を自然番組にも応用するといういう。
ヒーロー(=生きもの)に出会い、その「目的」(たとえば食べ物を探す)を描く。
そこに「敵」や「試練」を与え、果たして「生き延びるか否か」という緊張感をつくる。
そして最後に“twist(ひねり)”―たとえば「棘の防御」「母の知恵」など、種の持つ驚くべき適応を見せて、視聴者を物語の“解放”へ導く。
セッションの終盤で紹介されたデータが印象的だった。
『Blue Planet II』放映後、
- “Plastic recycling”の検索が55%増加
- “Ocean plastic”に関する検索が2倍
- 海洋保全団体へのアクセスが169%増
という具体的な行動変化が起きたという。
映像表現が、視聴者の“意識”だけでなく“行動”を動かした事例だ。
「伝える」と「煽らない」の間
物語の力は大きい。視聴者の心を動かす映像は、共感を呼び、関心を喚起する。しかし、その力を持つ者には、同時に「表現の責任」が問われる。BBC Studios のスピーカーと、セッション後に制作段階での倫理的配慮と事前チェック、そして放映後のモニタリングの重要性について議論した。
BBCには、制作前・制作中・編集段階を経るたびに、映像表現が持つ影響の潜在リスクを評価・チェックするガイドラインと審査制度が複数内在しているという。たとえば、出演協力者の同意取得、匿名化・プライバシー配慮、リスクの高いシーンの扱い方、視聴後の反響フォローアップなどだ。
ストーリーを紡ぐことは、感情を動かすこと。感情が動くと、行動変容も伴うことも。
だがそれが“保全”につながるのか、“自然を壊す行動”に傾くのかは、語り手の設計次第ではないだろうか。
私はこのセッションを通じて、改めてメディアや物語の影響力の大きさを感じた。
だからこそ、表現にはガイドラインと検証の仕組みが必要であることも、再認識した。
ROOTsでは、メディアや映像制作者と共に、動物の描写がどのように視聴者の行動や認知に影響するかを検証し、リスクを事前に防ぐためのガイドラインと診断ツールを開発している。
BBCが番組制作で実践しているように、倫理と創造性の両立を“現場のルール”として根づかせることが、これからの時代のクリエイティブの責任だ。
関連リンク
🔗 BBC Studios – Natural History Unit
🔗 ROOTsブログ|『世界最大の自然保護会議で「メディア×自然」国際合意が採択』
一般社団法人Rooting Our Own Tomorrows
安家 叶子