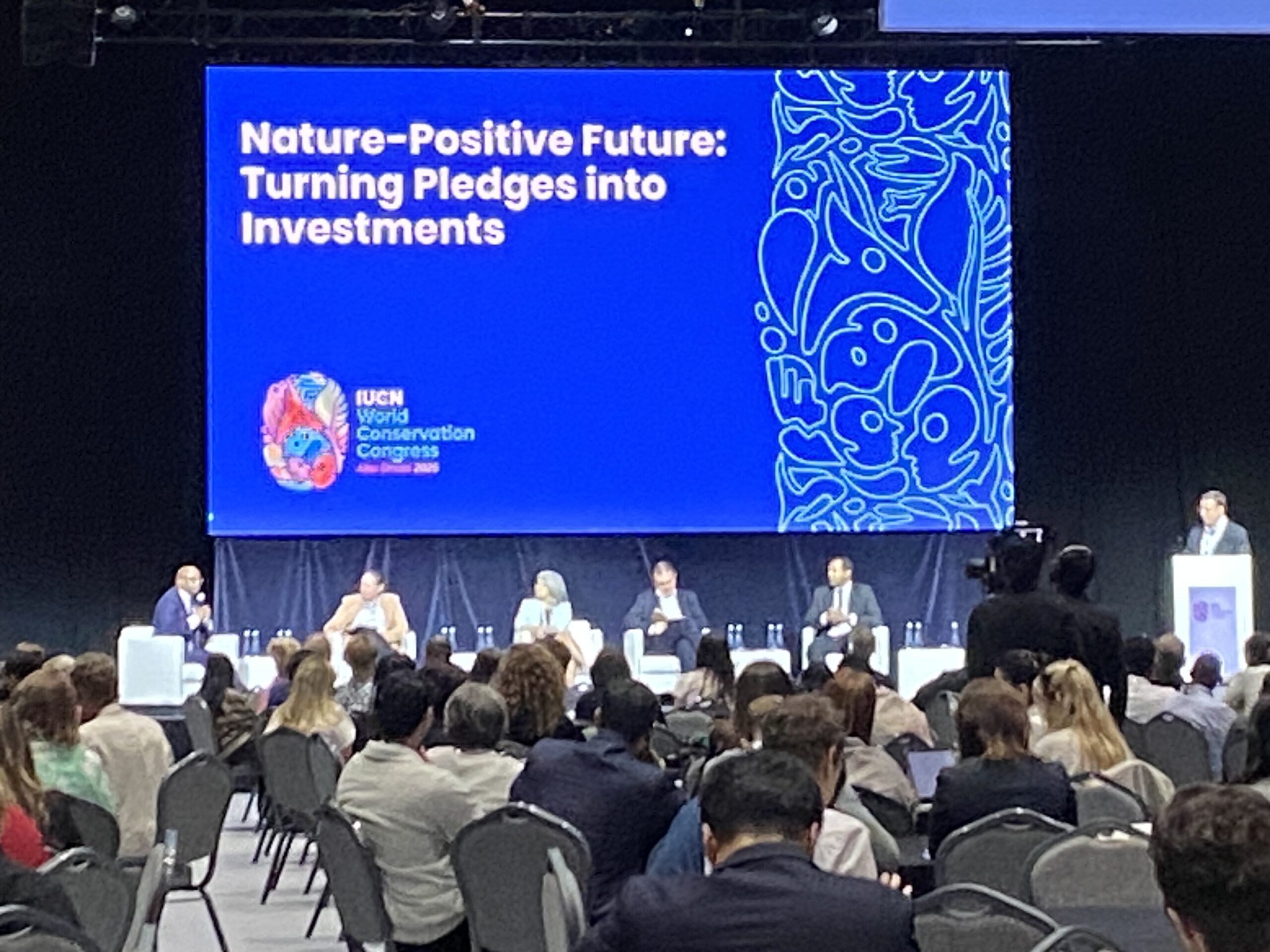非常になじみの深い生物多様性ホットスポットが更新されるというので、パビリオンのセッションに参加しました。公表されていたスケジュールより25分早く始まりました。理由:内容が多いから!
世界地図の中で、生物多様性の保全にとって特に重要なところはどこかを表す生物多様性ホットスポット。ノーマン・マイヤーズ博士が1988年にアイデアを発表し、1999年に25か所のホットスポットが発表され、2004年に34か所拡大されたときに「ジャパン」もその中に含まれました。現在は36か所の生物多様性ホットスポットがあります。コンサベーション・インターナショナルが活動する優先地域の根拠としました。日本政府も出資するCEPF(Critical Ecosystem Partnership Fund)は、ホットスポットを単位として保全活動に取り組んでいます。Natureに論文が出版されてから今年で25年。自然の状況の変化や、データの収集・解析のテクノロジーの進歩を反映させて、生物多様性ホットスポットの更新をすると発表されました。
この更新では、生物多様性の豊かさと危機性をエコリージョンを単位に評価するという中核のコンセプトは維持しながら、レッドリストのCR、EN、VUに加えてNTを含める、Area of Habitat (AoH)、STAR、経済的優先度などを検討に加える、など、評価方法を進化させて更新作業を進めるとのこと。ホットスポットの入れ替えがあるかもしれません。結果は12か月くらいで発表できるか、とのこと。データの更新や解析のスピードが上がっているので、毎年更新していく計画の様です。発表が楽しみです。
IUCN日本委員会 副会長/IUCNアジア地域委員会 副会長
名取洋司