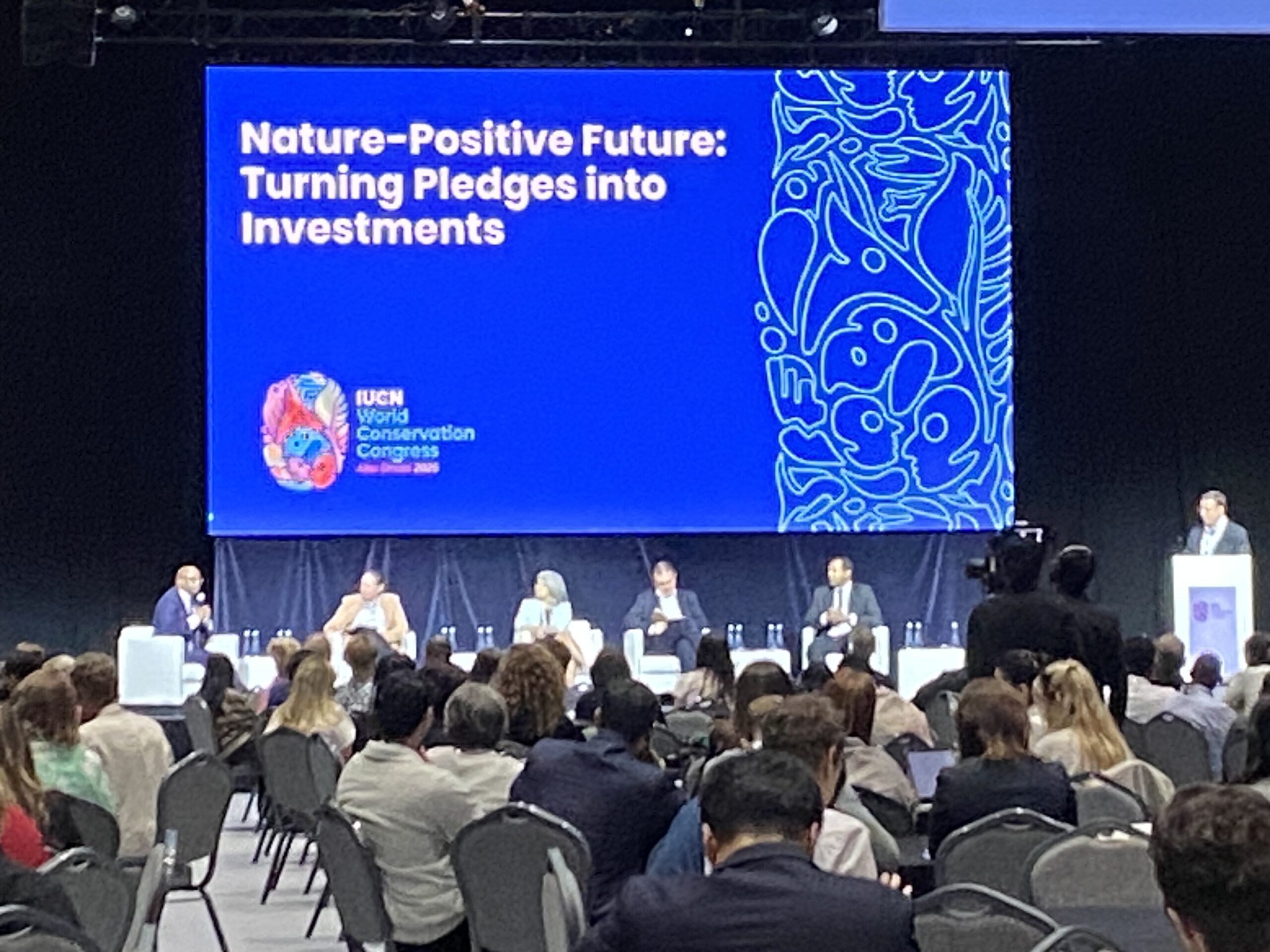国際環境ガバナンスにおけるユースの役割は、「将来の担い手」としての象徴的存在から、政策決定や資金運用、職業的実践を通じて「社会構造の変革主体」としての認識へと急速に変化しつつある。今回参加した三つのセッション、フォーラム――「Engaged Youth in International Environmental Policy-making」、「Funding Future: Youth-led Pathways for Biodiversity」、「Youth Development in the Green Jobs Sector」――は、それぞれ政策参画、資金メカニズム、グリーンジョブと焦点は異なるものの、共通して「ユースが持続的に社会変革の担い手となるには何が必要か」という問いを投げかけていた。これらの学びから明確になったのは、ユース参画の有効性は、政策・資金・雇用という三つの要素が相互に連動することによって最大化されるということである。
- 政策:学びと実践をつなぐ「参画型教育」の重要性
国際環境政策形成におけるユース参画では、教育と実践の接続が重要なテーマとして浮かび上がった。IUCNにおけるモーション開発や政策交渉を教育プログラムに組み込み、学生自らが提案や議論に関わる事例は、政策形成の現場を「学びの場」として再定義していた。このように、実際の意思決定過程に参加することが、政策リテラシーの向上だけでなく、自らの提言が社会に反映される経験となることが、ユース参画の持続性を高める重要な要素である。
一方、日本におけるJYPSなどのユース団体の活動を振り返ると、政策提言は行われているものの、教育現場や行政との体系的な連携はまだ限定的である。政策活動を一部の熱意ある個人に依存するのではなく、教育制度や制度的枠組みに組み込み、経験を「一時的な活動」から「体系的な学び」へと転化する仕組みづくりが求められる。
- 資金:ユース主導の「共創型ファンディング」への展開
生物多様性保全の分野では、ユース自身が資金配分やプロジェクト評価に関与する「youth-led funding mechanisms」が注目されていた。単なる外部支援に依存するのではなく、資金を自立と影響力の基盤として活用する視点は、新しい可能性を示すものである。
しかし、短期的助成やドナー依存的なスキームに留まる現状では、活動の持続性や社会的信頼性に課題が残る。日本においても、ユース団体の活動資金は多くが短期的で、政策提言やプロジェクトを長期的に継続するための基盤にはなっていない。資金の透明性や持続性を確保し、ユース自身が設計・運用に関わることで、単なる「受け手」から「資金構造の担い手」へと進化することが可能であり、社会変革に対する主体性が高まる。
- 雇用:活動から「キャリア」への橋渡し
グリーンジョブ分野では、ユースが環境活動を「ボランティア」から「職業的発展」へと接続する視点が強調された。政策提言やプロジェクト経験を自らの職業的キャリアに統合することで、活動の持続性と影響力が格段に向上する。
日本では「グリーンジョブ」や「サステナビリティ人材」という概念がまだ十分に浸透しておらず、政策や教育活動を職業的キャリアに結びつける制度的な仕組みは限定的である。教育、産業、政策を統合したキャリアパスの明示が、ユース参画を一過性の熱意で終わらせないための鍵となる。

- 三位一体モデル:政策・資金・雇用の相乗効果
これら三つの要素は、個別に取り組むだけでは十分な効果を生まず、相互に補完し合う「三位一体モデル」として構築されることが必要である。政策への参加は意思決定へのアクセスを提供するが、資金や雇用の基盤がなければ活動の継続性は担保されない。逆に、資金や雇用があっても政策に影響を与える手段がなければ、社会変革にはつながらない。したがって、ユース視点を政策決定構造に制度的に組み込み、資金スキームを恒常的に整備し、環境教育とグリーンジョブ育成を国家戦略と連動させることが、持続可能な地球環境ガバナンスの基盤を形成する。
- 日本のユースとしての展望
政策提言活動を行う立場からは、今後以下の三点が重要である。第一に、教育現場と行政を連携させた「政策参画型教育」の拡充。第二に、ユース主導の助成制度や共同資金モデルの創出。第三に、グリーンジョブへの接続支援とキャリア形成支援の強化である。
これにより、ユースは単なる声の届け手ではなく、政策・資金・職業の各構造の中に自らの影響力を恒常的に組み込み、社会変革の持続性を担保できる。政策、資金、雇用の循環が機能することで、ユースは次世代の象徴ではなく、現在進行形で持続可能な社会を共創する主体として立ち現れる。
Japan Youth Platform for Sustainability (JYPS)
嶋田恭子