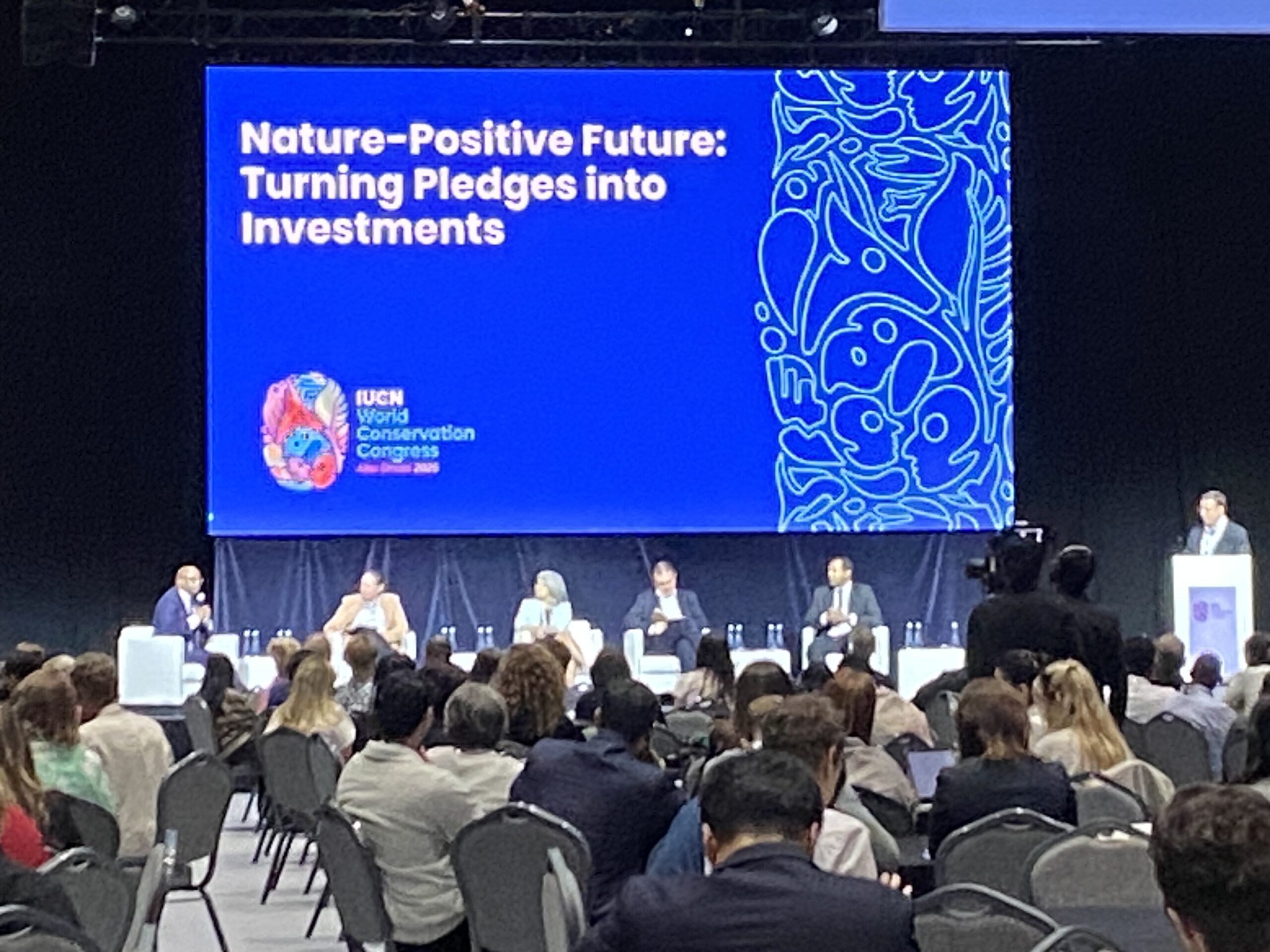1.セッションの概要
本セッションは10月11日、Business Pavilionで開催された。テーマは「Evolution of the Blue Economy(ブルーエコノミーの進化)」であった。登壇者には、商業銀行、NGO、スタートアップなどが名を連ね、業界を超えた議論が行われた。
2.セッションの内容
(1)FABによるブルーボンドの展開
最初に登壇したのは、アラブ首長国連邦最大の金融機関First Abu Dhabi Bank(FAB)の代表である。同銀行は2023年に中東で初めてブルーボンドを発行し、2025年には第2回発行を完了したと報告した。(FAB issues $20m blue bond following successful debut in Aug)
これにより、同社の持続可能な金融関連の債券発行は総額40億ドル超に達したという。
調達資金は、海水淡水化施設や下水再利用、グリーン電力によるバッテリー蓄電などに使われ、UAEの「Water Security Strategy 2036」の実現を後押ししている。
代表は市場の成長にも言及した。2018年から2022年にかけて世界で26件・総額30億ドルのブルーボンドが発行され、現在は累計150億ドル超に達している。2030年には年間発行額100億ドル規模に拡大すると見込まれ、10年前のグリーンボンド市場とほとんど同様な成長軌道をたどっているという。
(2)WWFによる現状分析
議論に先立ち司会者であるWWFのNicholas氏がブルーボンドに取り組む意義を語った。彼は海が地球最大の炭素吸収源でありながら、急速に劣化している現状を指摘した。過去50年で海洋生物の個体数が約半減し、マングローブ林・サンゴ礁・海草藻場などの重要な生態系が失われつつある。これは単に環境問題にとどまらず、食料安全保障や経済の安定を脅かす要因である。
さらにWWFの試算では、上場企業の約3分の2が海の劣化に関連する財務リスクを抱え、約8.5兆ドルの経済価値が危機にさらされている。Nicholas氏は「海洋の回復は環境保護の問題にとどまらず、経済を守る行為でもある」と述べ、金融の関与を促した。
(3)議論の焦点
本セッションでは、ブルーボンドおよびブルーエコノミーをどのように拡大していくかが中心的なテーマとして議論された。登壇者たちは、持続的な資金循環を実現するためには、金融機関・企業・政府・国際機関など多様な主体が共通の枠組みのもとで協働する必要があると強調した。議論の焦点となった課題は大きく二点に整理できる。
第一に、制度的基盤の整備である。各国の政策を整合させ、国際的に通用する基準や認証制度を確立することで、投資の信頼性と透明性を高める必要があるとされた。
第二に、共通の評価指標の欠如が挙げられた。気候変動対策における「CO₂排出量1トン」に相当するような、自然資本や生態系の価値を測る共通メトリクスが存在しないため、投資効果を定量的に示すことが難しい。このため、金融機関や投資家が自然関連のリスクとリターンを正確に判断できる仕組みを整えることが急務であるとされた。
全体として、ブルーエコノミーの拡大には「信頼できるルール」と「物差し」の構築が欠かせないとの認識が共有された。
(コメント)
FABの動向に関して、一般的に銀行は、債券市場において発行体と投資家の仲介者としての役割を担うことが多い。そのため商業銀行であるFABが自らブルーボンドを発行している点は興味深いと感じた。
またセッションの中でも特に印象的であったのは、「分かりやすい指標の必要性」に関する議論であった。
登壇者らは、ブルーボンドのさらなる拡大に向けた課題として、自然の価値を定量化する共通指標の欠如を最大の障害に挙げていた。例えばCO₂排出量には「1トン」という共通単位が存在するが、生物多様性にはそれに相当する尺度がまだ確立されていない。銀行や投資家がリスクと利益を判断し、資金を流すためには、「物差し」の開発が不可欠であるという意見に、多くの出席者がうなずいていたのが印象的だった。
自然や生態系の価値はしばしば抽象的で、専門的な議論にとどまりやすい。そのため、一般の人々が理解し、共感をもって行動につなげるには、誰もが納得できる形で「自然を測る尺度」を提示することが重要であると感じた。
環境問題の多くは一部の専門家や活動家だけでは解決できず、社会全体が共通の認識を持ち、協働して取り組むことが不可欠である。その意味で、自然を定量化する指標を整備することは、社会的合意を形成するために解決するべき課題でもあるといえる。
もちろん、指標を単純化することにはリスクも伴うが、理解を広げる第一歩としての価値は大きい。複雑な問題を複雑なまま理解できることが最善であるというのは言うまでもないが、これを広く一般に求めるのは現実的ではない。誰もが行動を起こせるような分かりやすい形で提示することが、今後のブルーエコノミーの発展にとって重要になるだろう。
筑波大学 世界遺産学学位プログラム/IUCN-Jインターン
作森元司郎