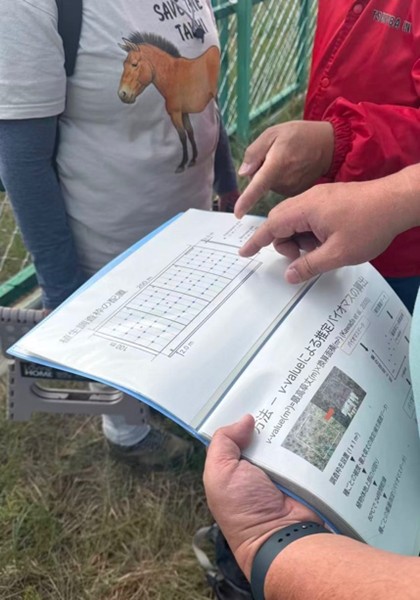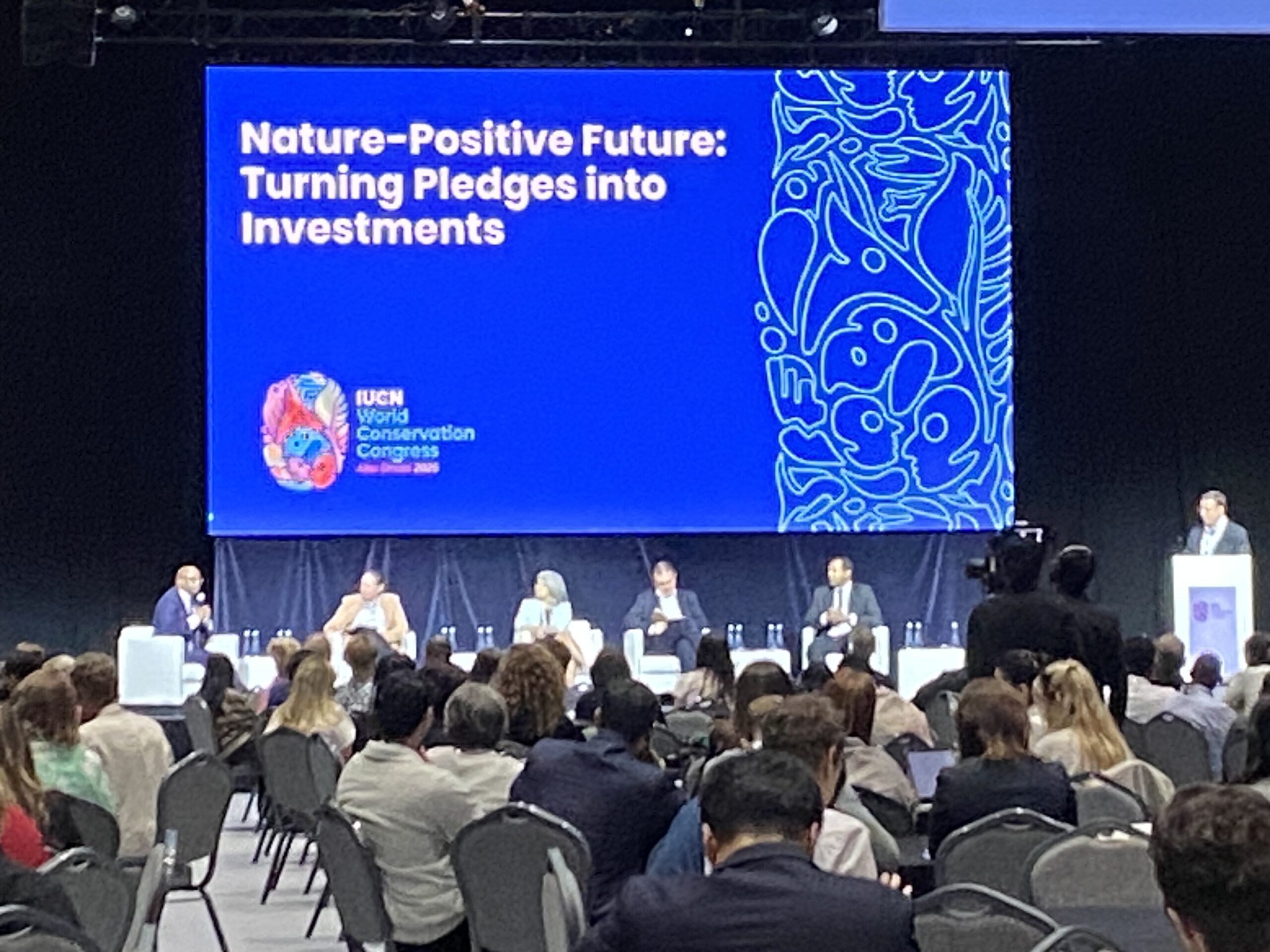
フォーラムNature-Positive Future: Turning Pledges into Investmentsに参加しました。
このセッションは、元国連開発計画(UNDP)総裁のアヒム・シュタイナー氏がモデレーターを務め、ルクセンブルクの環境・気候・生物多様性大臣が基調講演を行いました。
考えさせられたのは、ボツワナ環境観光大臣が「ワイルドライフエコノミー」への投資が重要と話し、アジア開発銀行環境局長の渡辺陽子氏 が、例えばマングローブの保護も地域住民への投資であると話したのに対し、国連資本開発基金事務局長が、地方銀行による少額の投資が、地域の事情に合った事業の運営ができると発言していたことです。
世界規模の大きな経済の話に、地域住民の視点が投げ込まれた印象です。
少額な支援で成果
私たち野生生物保全論研究会(JWCS)は野生生物の生息地を保全するプロジェクトとして、コンゴ共和国でゾウによる農業被害に悩む村で、代替の収入源として養蜂教室を開催しました。そして村出身の講師と受講生がはちみつの生産者組合結成まで到達することができました。その費用は、日本の助成団体からの助成金とクラウドファンディングによるもので、1年間の予算規模は100万円未満でした。それに至るまでに、栽培期間が短くその分ゾウの被害のリスクが低い農作物の導入や観光土産用の工芸品なども試しましたが、結局は村人が関心をもち、村内にリーダーがいる養蜂事業だけが継続しました。
このような事業に投資をするならば地方銀行による地域の人間関係を理解した少額投資が結果を出すという意見はとても納得がいきました。
野生生物の経済利用の一つの側面
林業や漁業は野生生物の利用の一つですが、ボツワナ政府が推進する「ワイルドライフエコノミー」は、エコツーリズムや野生動物の観光狩猟のようなビジネスです。これは経済性を優先しがちで、野生生物の保全と両立する持続可能な範囲に収めることが難しい事例が多々指摘されています。
この「ワイルドライフエコノミー」は南部アフリカ諸国に支持されており、象牙の取引再開もその一つです。象牙は2016年のIUCN総会で「象牙国内市場閉鎖」が決議され、その直後のワシントン条約締約国会議でも決議されました。その後おもな象牙消費国は国内での象牙の売買を禁止する法律を整備したため、日本は最大の合法の象牙市場がある国になってしまっています。
多くのアフリカのゾウ生息国は象牙国内市場閉鎖を支持しており、南部アフリカ諸国とは意見が対立しています。それでも南部アフリカ諸国が象牙をあきらめないのは、日本のように象牙ビジネスがまだ残っているからです。
日本からの「ポジティブ」な提案
そのため日本からの発信は重要です。JWCSは材質の特性から「象牙でなければ」と言われてきた和楽器で、初めて象牙代替品の音色を披露するコンサートを10月31日に開催します。竹を原料とした新素材やセラミック製の筝爪や植物原料配合の筝柱を使用します。そして箏とセネガル出身の打楽器奏者のコラボレーションも披露します。日本のテクノロジーが日本とアフリカの伝統音楽をつなげ、アフリカの国々の野生生物の利用をめぐる対立の解消に貢献し、ゾウの密猟防止につながる「ネイチャーポジティブ」の実践です。
コンサートの詳細は https://www.jwcs.org/event/3541/
認定NPO法人 野生生物保全論研究会 事務局長 鈴木希理恵