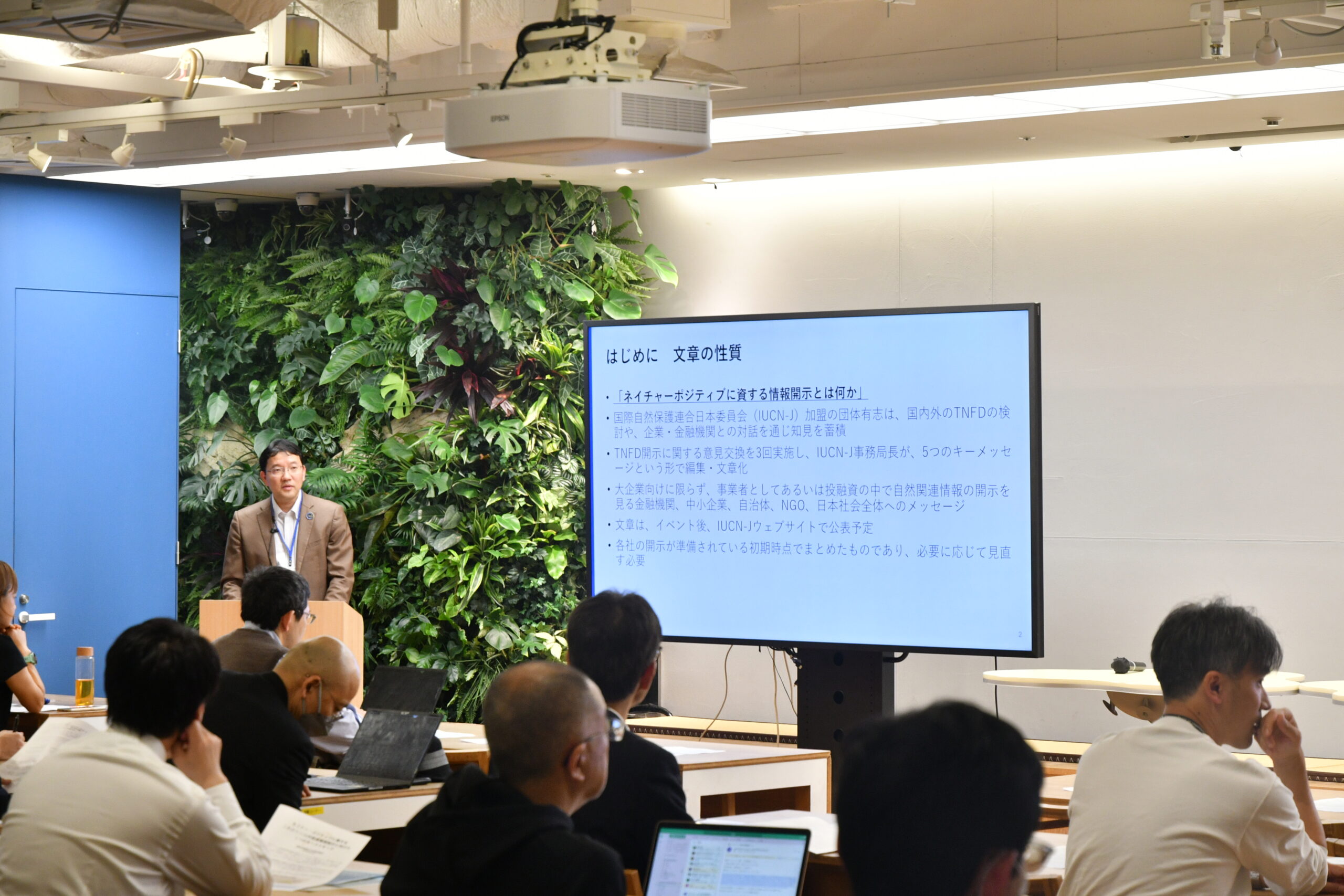IUCN-Jでは9/1(月)に、生物多様性関連情報の収集・利活用に関する意見交換会を開催しました。近年、生物多様性クレジットやTNFDなどの枠組みを通じて、企業や地方自治体がネイチャーポジティブに向けて動き出しています。こうした活動を適切に評価するための指標づくりにおいて、「どこに・どのような生物が・どれくらい存在するのか」といった生物情報の重要性はますます高まっています。
今回の会合には、IUCN-Jメンバーに加え、協定団体である国立環境研究所も交えた意見交換会を実施しました。生物多様性モニタリングや指標作りに関する各団体の取り組みを紹介しました。その後、現地での生物データ収集という川上の段階から、評価指標としての利活用という川下の段階に至るまで、様々な課題や意見、さらには必要とされる政策について活発に議論が交わされました。中でも「担い手不足」はどの団体からも共通課題として指摘され、公共事業であってもデータ収集に対して一定の対価を認める仕組みが必要ではないか、という意見も出されました。
議論の中で特に印象的だったのは、「数値化の進展と同時に、自然と実際に触れ合う経験を軽視してはならない」という指摘です。生物多様性に関する指標が作成され、数値化が行われていく中で、数値の大小がそのまま生物の価値に直結するような錯覚を生みかねません。その生物が「そこに存在している」という絶対的な価値を忘れないためにも、現場で自然にふれる体験を怠ってはいけないと感じさせられました。
休憩時間にも参加者同士の交流や議論が絶えず行われ、企業や国が今後ネイチャーポジティブを実現していくうえで、どのような仕組みづくりが必要かについての認識を深め合う場となりました。今回の意見交換会を一つの契機として、今後も継続的に議論を重ね、現場の実践や政策形成に反映していくことの重要性を改めて実感しました。
IUCN-Jインターン生
今川春佳