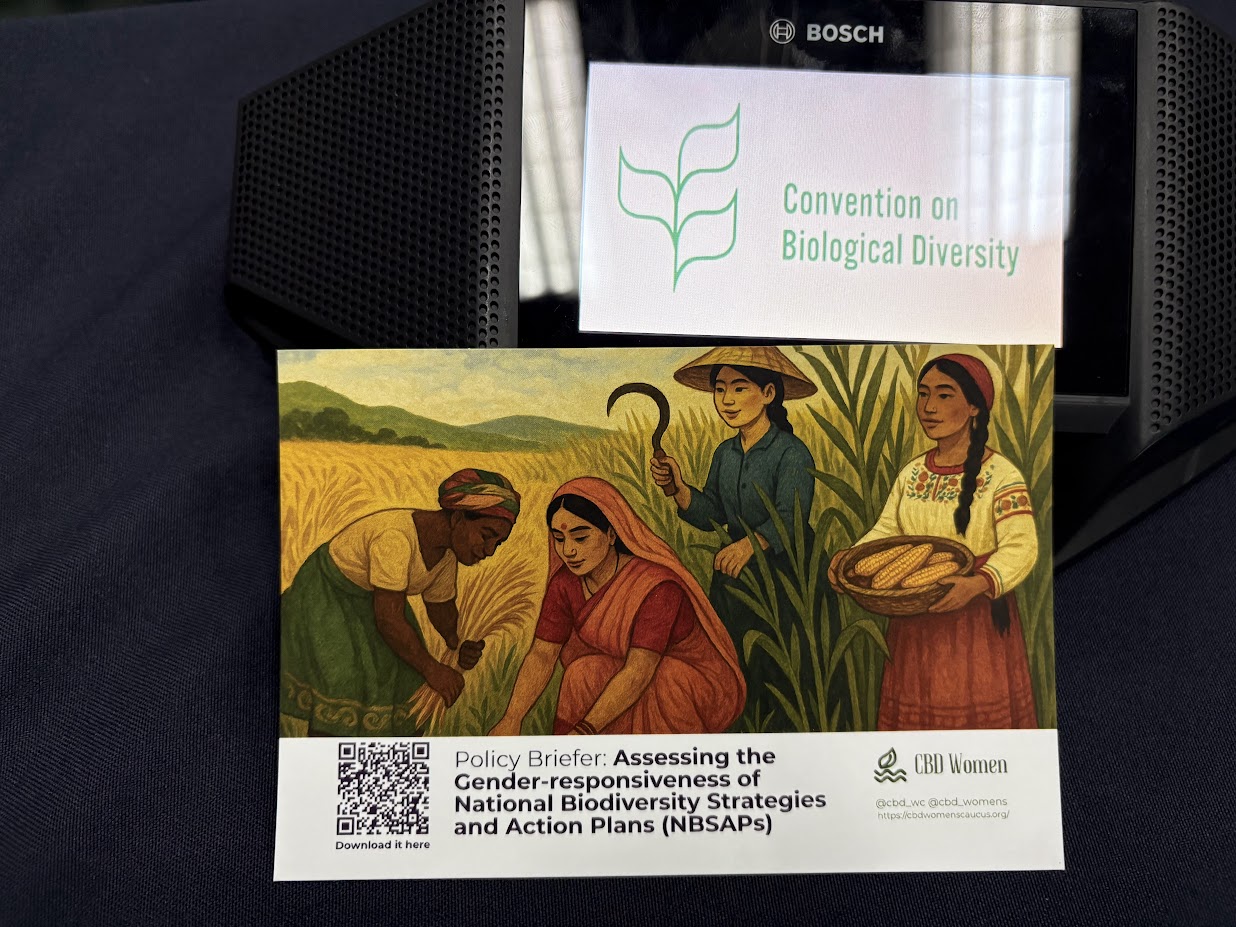生物多様性条約第27回科学技術助言補助機関会合(SBSTTA27)は3日目を迎えました。会場では、森林、気候変動、健康、そしてIPBES(政府間科学政策プラットフォーム)など、主要なテーマが議論されましたが、科学的助言の場であるはずのSBSTTAにおいても、政治的な駆け引きや手続き上の議論に時間を取られる場面が目立ち、会場には次第に疲労感が漂っていました。
午前:森林は順調に、気候変動は手続き論で停滞
午前のセッションでは、まず「森林に関する作業プログラム」が審議されました。この議題は比較的順調に進み、各国が森林の生物多様性保全の重要性と、これまでの取組の継続を確認する形で合意形成が進みました。
一方で、「気候変動と生物多様性」に関するコンタクトグループでは、冒頭から手続き論が続きました。付属書(Annex)の改定手続きの確認だけで約1時間半を要し、本論に入るまでに多くの時間が費やされました。
科学的な助言を目的とするこの会合で、政治的な発言や立場調整が前面に出る場面も多く、議論の熱が感じられないまま時間だけが過ぎていくような印象でした。
午後:健康とIPBES、そして歩み寄り(合意)のない議論
午後は「生物多様性と健康」に関するステートメントの紹介から始まりました。
人間の健康と自然環境との関係性という本来重要なテーマにもかかわらず、発言は短く、会場全体として議論が広がる雰囲気には至りませんでした。
続いてIPBESに関する議題に移り、評価報告書に関するカンファレンスルームペーパー(CRP)が検討されました。
しかしこの議論でも、IPBES総会で採択された政策決定者向け要約(SPM)の扱いをめぐって意見が分かれ、時間を費やしました。
一部の国は、締約国会議で求められた評価作業に対して、報告書を「歓迎(Welcome)」ではなく「留意(Take note)」にとどめたいと主張しました。これに対し、「科学技術助言機関が科学的報告を“歓迎”できないのは本末転倒ではないか」との指摘もあり、やり取りが続きました。
こうした場面は決して珍しいものではありませんが、科学的根拠をもとに合意を形成すべき場が、政治的配慮に縛られ、議論が進まない現実には、参加者の多くが疲れを隠せない様子でした。
また、議論の長期化により、オブザーバーの発言時間が削られ、NGOや研究者の参加スペースが縮小している点も懸念されます。
夜:最多のサイドイベントも、議論の重さが影を落とす
夜には、今回最多となる7つのサイドイベントが行われました。
コンタクトグループは、「リスクアセスメント」と「既存作業プログラムの今後の扱い」のテーマで開かれました。日中の交渉の影響を受け、出席者の疲労も見られました。途上国の交渉官が一人で複数の議題を担当している事情もあり、コンタクトグループは同時開催を避け、順番に開催する対応が取られました。現場では実務的な工夫が重ねられつつも、全体として議論のペースの遅れは否めません。
朝:IUCN関係者会合―停滞の中での前向きな議論
一方、朝の時間にはIUCN関係者の意見交換会が開かれました。事務局、会員団体、専門委員会、そして私たち国内委員会(IUCN-J)が一堂に会し、現在の会合の進行に対する懸念と、それにどう向き合うかについて真剣な議論が行われました。科学的助言機関の本来の役割をどう取り戻し、政治的な議論に埋もれがちな科学的知見の重要性をどう発信していくか――。参加者の発言には、現状に対する危機感と同時に、IUCNというユニークな存在が果たすべき責任への強い自覚がにじんでいました。

朝のIUCN関係者会議。多くの方が、先週のIUCN世界自然保護会議にも参加していました。
SBSTTA27の議論は、引き続きCOP17に向けた勧告文書のとりまとめに向けて続いています。しかしその過程では、科学的根拠に基づく合意形成の難しさと、国際交渉の現実の厳しさが浮き彫りになっています。IUCNとしては、こうした停滞に抗いながら、科学的知見と現場の声をつなぐ役割を果たし続けていくことが求められています。
国際自然保護連合日本委員会 道家哲平