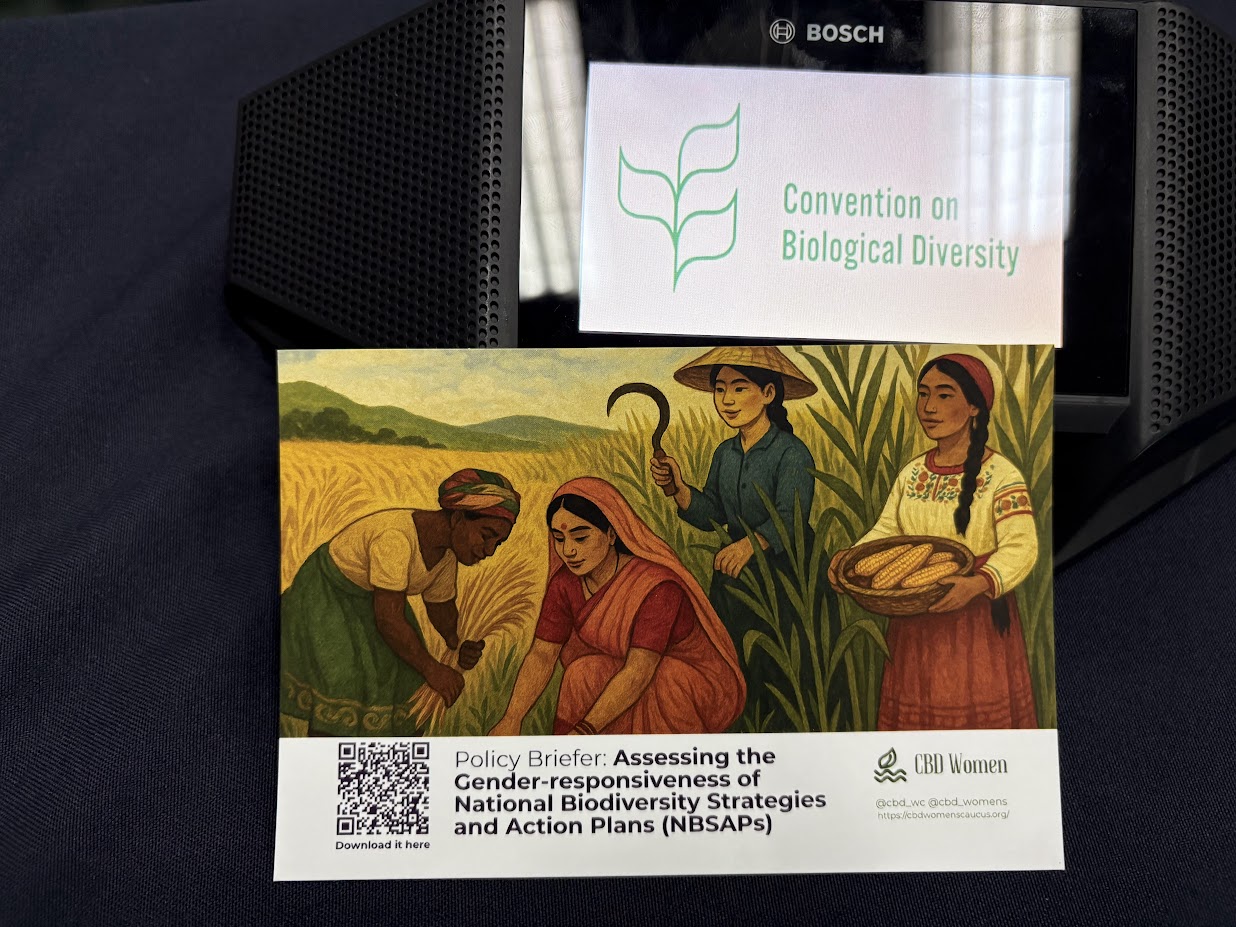
国際会議に参加する意義のひとつは、日本ではなかなか触れることのできない議論に出会えることです。今回、生物多様性条約第27回科学技術助言補助機関会合(SBSTTA27)の期間中に開催されたサイドイベント「Applying a human rights-based approach in line with Section C of the Kunming-Montreal Biodiversity Framework」も、まさにそのような場でした。
このイベントでは、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)が中心となり、生物多様性条約事務局(CBD)、グローバルユース・バイオダイバーシティネットワーク(GYBN)、CBD女性コーカス、先住民生物多様性フォーラム(IIFB)、UNEP-WCMCなどが共催し、人権ベースアプローチ(Human Rights-Based Approach, HRBA)を生物多様性政策にどのように取り入れるかを議論しました。
人権ベースアプローチとは何か
人権ベースアプローチ(Human Rights-Based Approach)とは、国際人権法に基づいて政策や制度を設計・実施する考え方です。すべての人が尊厳と幸福を享受できる社会をめざし、不平等や差別の是正を重視します。その中核は、国家や自治体など「義務履行者(duty-bearers)」が責務を果たす能力を高め、同時に市民や地域社会など「権利保持者(right-holders)」が自らの権利を主張し行使できる力を強めることにあります。
この考え方は、行政法と憲法の関係にたとえると理解しやすいでしょう。行政法が公益のために一定の裁量で規制や施策を行う仕組みを定めているのに対し、憲法はどのような公益目的があっても侵してはならないラインを権利として定めています。環境政策でいえば、行政が「環境を守ることが望ましいから行う」という発想は行政法的なものであり、「人が健全で豊かな自然環境(水や大気、生態系)を享受することは基本的な権利であり、国家がそれを保障する義務を負う」というのが人権ベースの発想です。
このアプローチは、地理的条件や貧困、ジェンダー、年齢、障がい、文化的・民族的背景などによって社会から排除されがちな人々の参加を保障し、地域に根ざした協働的なプロセスを通じて、人権を実質的に進展させていくことを目指しています。
人権(権利)としての生物多様性を政策にどう組み込むか
冒頭では、OHCHRが作成したブリーフィングノートが紹介されました。この文書は、人権ベースアプローチを各国の生物多様性国家戦略や30by30目標の実施に反映させるための指針としてまとめられたものです。単なる理念ではなく、「誰が、どのように恩恵や負担を受けるのか」を明確にし、公正な意思決定を進めることの重要性が強調されました。
スウェーデンの代表は、「保護地域作業計画など、既存政策に人権の視点を入れていくことが重要」と述べ、CBD事務局とOHCHRの連携強化を提案しました。アルメニアは、河川漁業の全面禁止政策を見直し、地域共同体の知見や女性の参画を取り入れて、持続可能な政策へと転換した経験を紹介しました。
ジェンダーの主流化と課題
CBD女性コーカスからは、各国の生物多様性国家戦略(NBSAP)におけるジェンダーの扱いが報告されました。トーゴやウガンダ、タンザニア、ヨルダンなどでは、女性の能力強化や自然資源へのアクセスの公正性を確保する取り組みが進められています。一方で、多くの国では「女性の参加が重要」との文言があるものの、実際の行動計画や予算化までは至っていないことが指摘されました。
コーカスの代表は、「COP17ではジェンダーアクションプランの進捗が評価される予定であり、成果をしっかりと検証することが重要です」と呼びかけました。

開会式の開始前に、パナマのフアン環境大臣(写真右の男性)が先住民地域共同体からの参加者に友人のように話しかけていました。日本でめったに見られない(?)とても印象的なシーンです。
若者と人権の接点
グローバルユース・バイオダイバーシティネットワーク(GYBN)は、資金調達の難しさや発言機会の少なさといったユースの課題を共有しました。ウガンダではユース向けツールキットを作成し、ブキナファソではストーリーテリングを通じた普及活動、インドネシアでは小規模資金での活動展開が行われています。
参加者からは、「ユース指標の実装(Operationalization)」や「世代間公正(intergenerational equity)」の理解を深める必要性が強調されました。
権利ベースの事業設計を推進するドイツ
ドイツ代表は、「このガイダンスは時宜を得たものであり、今後の生物多様性関連事業では人権ベースの考えを必ず組み込むべきだ」と発言しました。同国の国際協力事業(IKI)では、IFC基準に基づく社会・環境配慮を徹底しており、プロジェクト設計の段階から人権の視点を重視していることが紹介されました。
誤解を解き、実践へとつなげるために
質疑応答では、「人権アプローチは政府と対立するものではなく、参加と説明責任を確保するための枠組みである」という誤解の解消が必要であると指摘されました。また、資金不足や能力開発の課題、地方レベルでの取り組みの遅れ、環境保護活動家への圧力など、現実的な課題も共有されました。UN‐OHCHRは、環境人権擁護者への支援や能力強化を進めていると報告しました。
今後は、生物多様性条約第8(j)に関する新しい補助機関の場で、先住民や地域共同体が締約国と共に議論を進めることになります。参加者からは、「ガイダンス原則を実践と評価につなげ、真に包摂的な生物多様性政策を進めるべきだ」という声が上がりました。
日本への示唆:見えない格差に気づくということ
このサイドイベントを通じて印象的だったのは、「ジェンダー・レスポンシブアプローチ」や「ユース・レスポンシブアプローチ」と呼ばれる考え方です。これらは、ジェンダーや世代の格差が社会の仕組みや文化の中に埋め込まれており、当事者でない人ほどその不平等に気づきにくいという前提に立っています。その上で、政策や事業を設計する段階から、差別や排除が起きないよう対策を講じることを重視します。
日本でも、こうした「構造としての格差」への意識はまだ十分に根づいていません。また「権利」という社会を構成する基本の考え方を十分に理解できてないのではないかと感じます。世界各地で意思決定の場に女性や若者が少ないこと、環境や地域づくりの現場で意見を表明しにくい空気が残っていることなどは、私たちの社会にも通じる課題です。
人権ベースアプローチやジェンダー・ユースレスポンシブな視点を取り入れることは、単なる「公平性」や「多様性」の問題ではなく、持続可能な社会の基盤を再設計することに他なりません。生物多様性を守るための取り組みも、誰の声を中心に据えるのかという問いが重要と考えました。
国際自然保護連合日本委員会 道家哲平






















