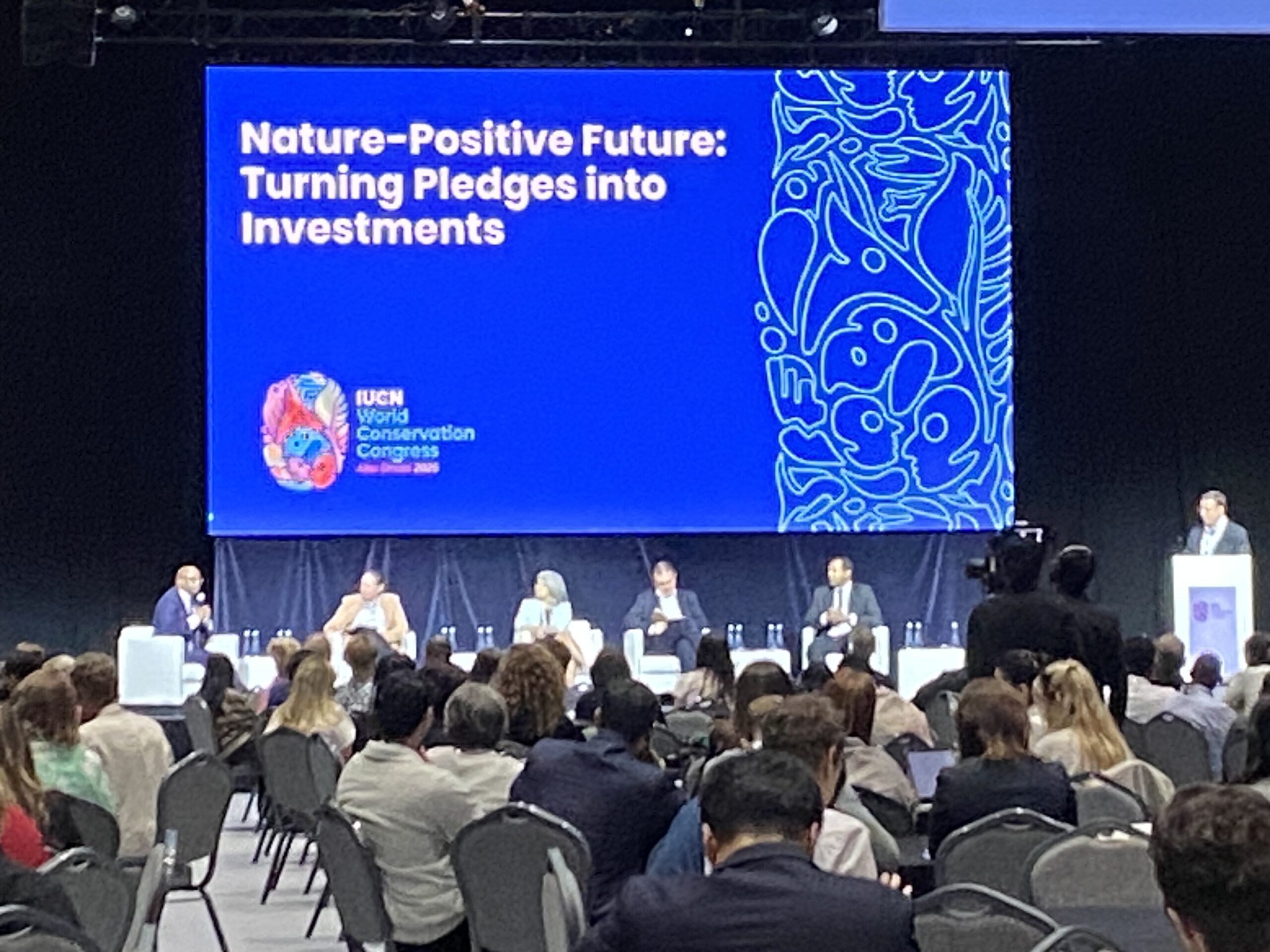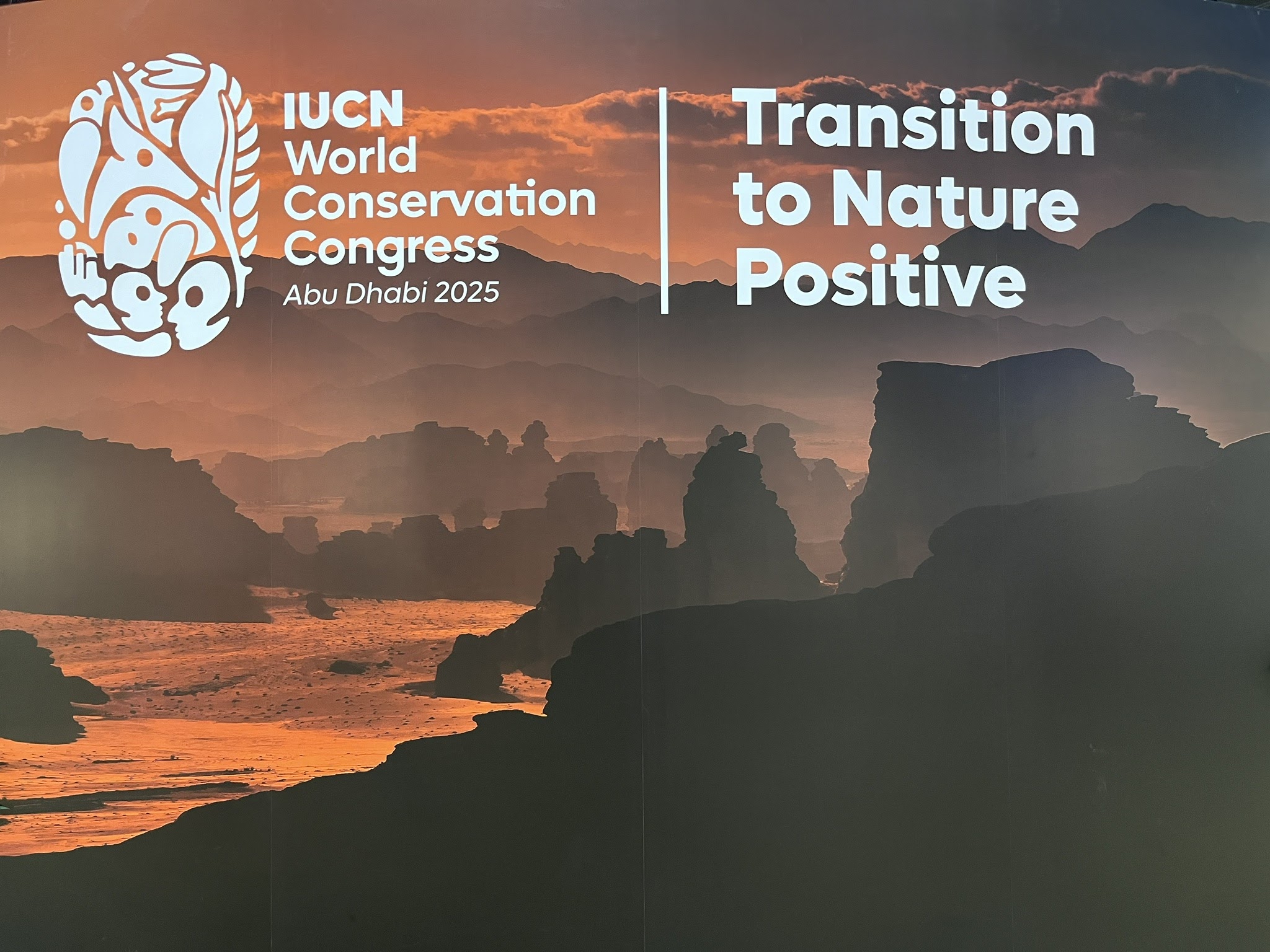
放課後の14時、子どもたちが「Falcon School」に通い、猛禽の世話や飛行訓練を学ぶ。そんな話をWCC会場でUAE現地の人から耳にした。育てたファルコンが市場で高値をつけることもあるという。
確かにUAEには、文化遺産としての鷹狩を保護することを目的に、理論・行動生理・倫理まで体系的に教える学校が複数存在し、伝統技術を次世代に継承している。
ファルコン(鷹)は、砂漠の民が生き抜くための狩猟のパートナーであり、UAEの国家紋章にも刻まれる象徴的な存在だ。2010年、ユネスコは「ファルコンリー(鷹狩)」を11か国の共同提案で無形文化遺産に登録され、「人間と自然との深い絆を伝える文化」として世界的に認知されている。この文化が教育やイベントを通じて若い世代へ受け継がれているのは、確かにポジティブな側面だ。
一方で、市場の広がりは無視できない。
UAEは長年にわたり合法的な猛禽類の主要輸入国の一つであり、Biological Conservation誌の分析によれば、1975〜2020年の合法取引の約40%がUAE向けだったとされる(The National, 2023)。
政府はファルコン・パスポート制度とCITES許可制を運用し、輸出入・所有履歴の追跡を整備している。近年は飼育下繁殖やハイブリッド個体の利用が増え、野生捕獲への依存は低下傾向にあるとみられる。
しかし、過去には野生由来個体の輸入記録もCITESデータに残り、紛争地や貧困地域を起点とする密猟・密輸が続いていることも報じられている(Mongabay, 2023)。
C4ADS/ROUTESの分析を紹介したThe Nationalによれば、2009年以降UAE当局が空港で押収した“鳥類”は35件。
メディアが問われる責任――ROOTsの視点から
もっとも、個体数の減少は生息地の劣化や送電線による感電など複合的な要因が絡んでおり、鷹狩文化そのものが減少の主因かどうかをここで議論するのは避けたい。
むしろ問題は、その周辺で形成される市場構造とイメージの拡散にある。
現地で話を聞く中で、印象的だった言葉がある。
「SNSでは、ファルコンを腕に乗せる姿が“かっこいい”とされている。」
InstagramやTikTokには、砂漠を背景に鷹を肩に乗せた投稿が多い。それは伝統の誇りを伝える一方で、メディアで「希少で高価な象徴」として描かれるたびに、飼育や所有への憧れという副作用も生む。それが行き過ぎると、現地外での所有需要や違法取引のトリガーが働く可能性がある。だからこそ、文化を伝える際には、保全・制度・倫理の文脈を欠かさず添える必要がある。
日本でも、動物が「かわいい/珍しい」と切り取られるたびに、視聴者の関心が所有欲へ転じるケースは少なくない。ROOTsでは、こうした“見せ方”が生む無意識の需要を抑えるために、放送・配信・広告などでの動物表現のリスクチェックとガイドライン策定を進めている。 文化や伝統の題材を扱う場合も、背景にある生態・制度・倫理を併記し、視聴者の想像が「飼いたい」ではなく「知りたい」に向かうような構成を提案している。
産業化が進めば、野生個体の採取圧や密輸のインセンティブを高め、「文化の名の下」で生態系を蝕む構造に変わってしまうおそれもある。
伝統とは、過去の形をそのまま再現することではなく、そこに内在する精神や価値を、時代とともに更新しながら次の世代へ引き継ぐ行為だと強く感じる。
“文化”の旗のもとで野生生物が持続不可能なレベルで取引されるとき、私たちはその境界をもう一度、慎重に見つめ直さなければならないのではないか。
参考(本文で触れた主要情報)
- 鷹パスポート(制度):UAE環境・気候変動省サービス案内(公式)
- 無形文化遺産(背景):UNESCO Intangible Heritage “Falconry: a living human heritage”
- 輸入規模・市場構造:The National(2023)
- オークション事例:The National・WAM報道(2025)
- 違法取引(調査):Mongabay(2023)、GI-TOC分析(2022)
一般社団法人Rooting Our Own Tomorrows
安家 叶子