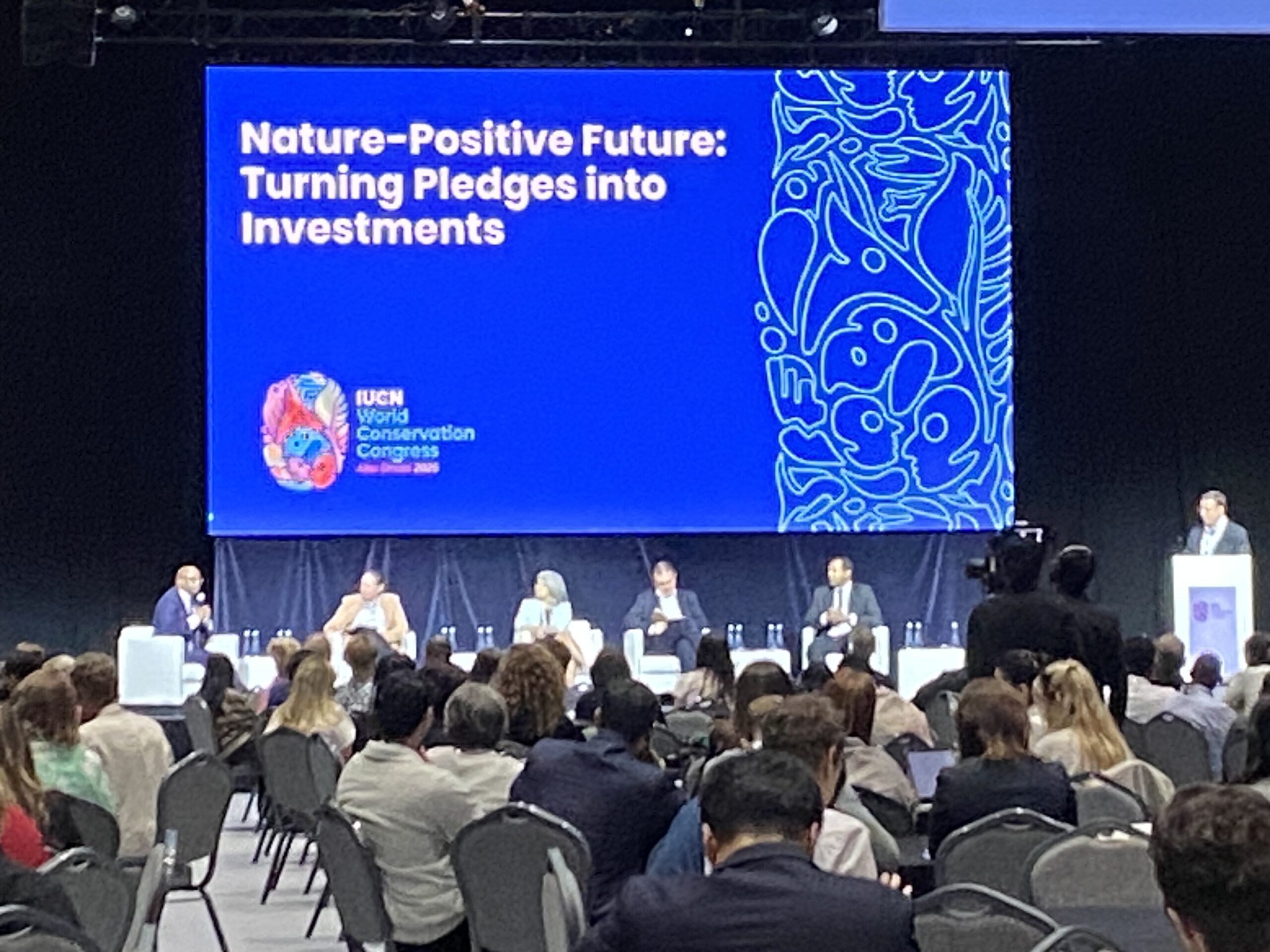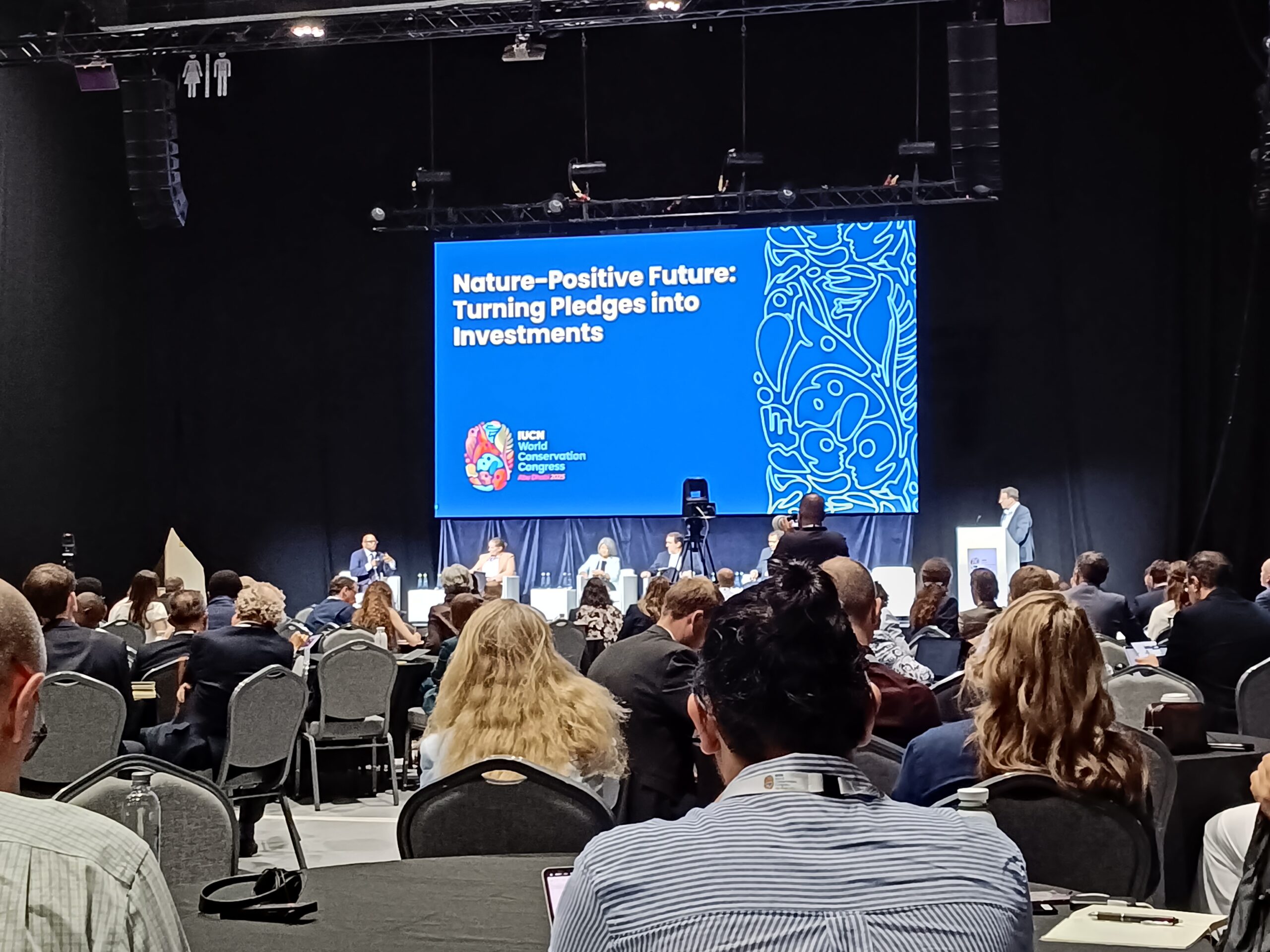
IUCN 世界自然保護会議(IUCN WCC)のオープニングセレモニー後、最初のセッションの一つとして、「Nature-Positive Future: Turning Pledges into Investments」が開催されました。本セッションは、自然保護への投資が論理的には正しいにもかかわらず、実行事例が少ないという問題に焦点を当てました。
セッション前半では、ルクセンブルクのセルジュ・ヴィルメス環境・気候・生物多様性大臣による基調講演が行われました。大臣は、地政学的な分断が強まる今こそ、国際協力と科学の力が不可欠であることを強調しました。また、自然保護への投資には公的資金に加え民間資金の動員が必須であるとし、投資家や民間企業に対し、信頼できるデータと事例を提供することで、投資が根拠に基づいた正しい行動であることを証明する必要性を訴えました。さらに、民間資金を呼び込むインパクトを生むためには、各国が政策としてまず自然保護への投資を率先して行うべきだと述べました。
セッション後半のパネルディスカッションでは、ここ数十年で自然保護に対する投資が停滞し、深刻な資金ギャップが生じている主な原因として構造的な問題があることが指摘されました。このギャップを埋めるためには、「公的資金と私的資金の両方をネイチャーベースド・ソリューションへ向ける必要がある」という認識がパネリスト全員の共通見解として示されました。
この現状を変え始めている事例として、ボツワナは、自然保護が国と地域コミュニティ双方の利益になるという認識に基づき、観光と環境を国の主要な収入源とするため、国を挙げて資金を導入していることを紹介しました。
また、世界銀行は、公的部門の18%にあたる55億ドルを自然金融に費やした実績を報告しました。その上で、資金を増やすこと以上に「現在ある資金をいかに効果的に使うか」が重要であるとし、その鍵として、①投資資金の価格設定、②信頼性と継続性、③資金へのアクセスのしやすさと正しい評価を行うための指標の三点を挙げました。
アジア開発銀行は、アジア太平洋地域のGDPの半分以上が自然資本に由来し、域内経済の70%が自然資源に依存する現状を踏まえ、様々なパートナーの資金を組み合わせ、民間資本を呼び込むためのファイナンスハブを創設し、グリーンボンドや生物多様性ボンドを通じて民間資金の動員を図っていると説明しました。
さらに、国連資本開発基金(UNCDF)は、現行システムが無視する地域コミュニティへの小規模・長期投資こそが不可欠であると主張し、少額の保証を供与することで現地銀行のリスク認識を変え、融資を拡大させた成功事例を紹介しました。
TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)は、自然課題を「企業の社会的責任」から「リスクとレジリエンス(回復力)」の問題として捉え直す重要性を強調しました。また、データと指標が企業の判断を促し、ある製薬会社が10億ドル規模の自然投資に踏み切った事例を示しました。
最終的に、自然保護への投資は「善意」ではなく、「経済的必然性」として実行可能な段階にあるという共通認識が示され、議論は締めくくられました。
このセッションに参加し、自然保護への投資に対する議論が「なぜ起こらないのか」から「いかに実現するか」という実効的な段階へ大きく進展していることを感じました。最も印象的だったのは、投資が停滞している原因が資金の不足そのものよりも、構造的な問題であるというパネリスト全員の共通認識です。特にUNCDFが指摘した途上国など地域コミュニティへの小規模投資の重要性を認識することができておらす、資金が必要な地域にこそ行きわたっていないという事例は、自然保護資金の中にあるアクセスのギャップという深刻な問題について非常に考えさせられるものでした。
現在、日本国内でもTNFDに取り組む企業が増加しています。これを受けて企業がTNFDに取り組んだということだけでなくその先の資金の流れや、ネイチャーベースド・ソリューションを実践する地域コミュニティへのお金の流れにも目を向けてみようとも思いました。
一般社団法人Change Our Next Decade
多計和真