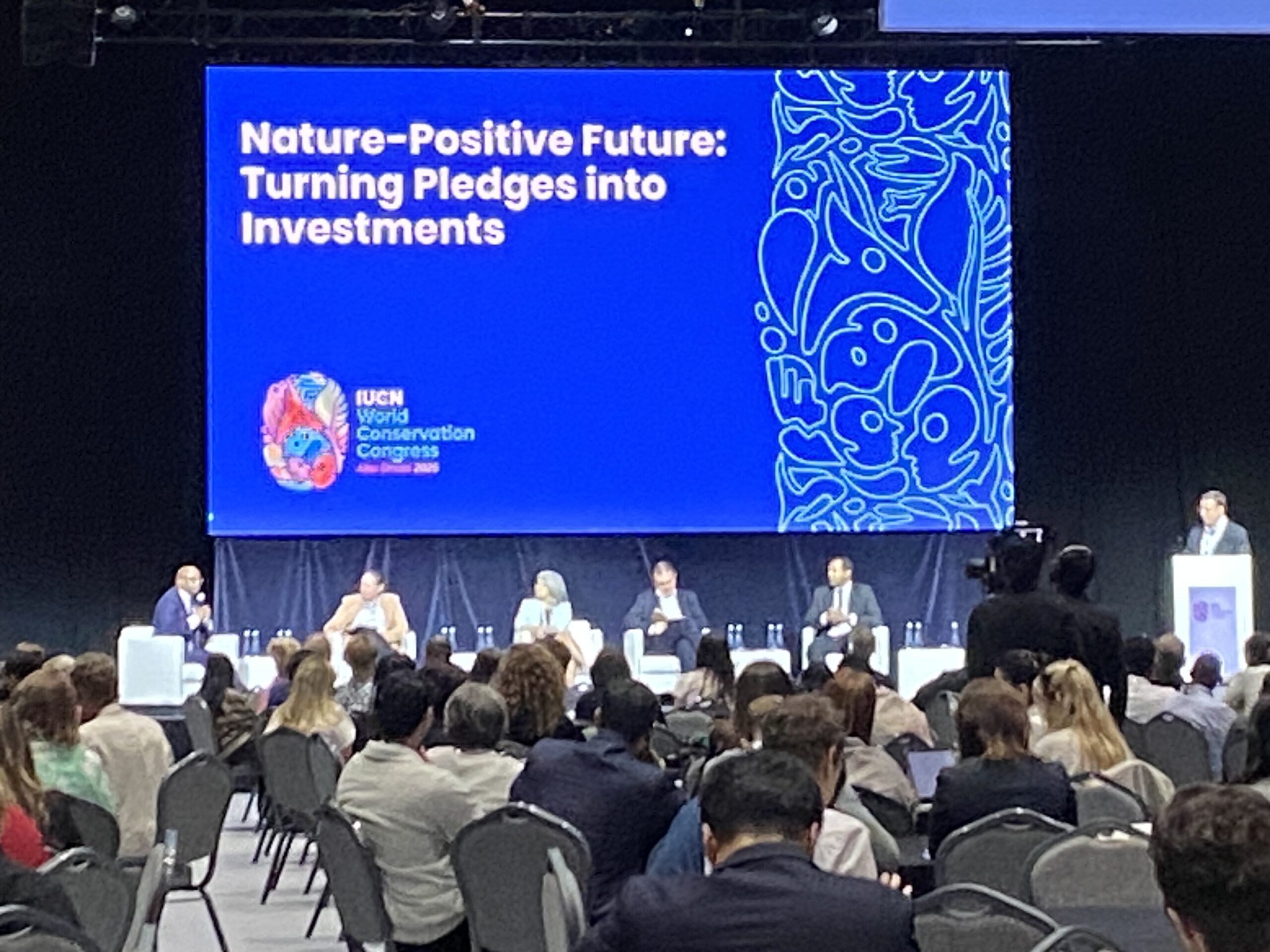一般社団法人ROOTs (Rooting Our Own Tomorrows)ではリサーチを担当している、宇都宮大学4年の杉山莉音です。色々な人とお話したり、初海外ということで様々な体験をしながら、WCCの参加を楽しんでいます。
一般社団法人ROOTs(Rooting Our Own Tomorrows)の活動紹介
日本では、爬虫類・両生類・哺乳類・鳥類など、幅広い野生動物がペットとして人気を集めており、その多くが絶滅危惧種に該当します。こうした需要の背景には、メディアの影響が大きく関係しています。
テレビやSNSで心を動かされた一つの作品が、社会の価値観や行動に大きな影響を与えることは多くあります。それくらい、メディアの我々への影響は大きいです。その影響力が、自然を守る人々を増やすきっかけとなることもあれば、時に自然や野生生物を失う形で作用してしまうこともあります。例えば、野生生物の魅力的な姿を描く際、野生生物を単に“かわいい”“飼いやすい”ペットとして紹介してしまうと、視聴者の飼育欲を刺激し、野生生物の利用や取引が増えることがあります。結果として、意図せず彼らを危険に晒すことがあります。
ROOTsでは、このようなメディアによる意識や行動変容を野生生物を守る行動へつながるよう、メディア関係者向けのガイドラインの作成や、専門家による監修・助言体制の構築などを実施しています。今回、WCCでは野生生物取引やメディアに関する情報収集を行っています。
UAE環境省のワシントン条約生物多様性専門部の方にインタビュー
WCCでは、各国のパビリオンを歩き回り、インタビューをしています。UAEの環境省ワシントン条約(CITES)生物多様性専門部の方に、国内の野生生物取引に関する現状や法律について、お話を聞く機会をいただきました。アラブ首長国連邦(UAE)では、かつてライオンやチーターなどの大型肉食獣を個人が飼育する事例が見られたそうです。しかし近年、国家レベルでの法制度整備と監視体制の強化により、こうした行為は急速に減少しています。UAEが進める野生動物保全と違法取引防止のための主要な取り組みについてのインタビュー内容を6つ紹介します。
-
法制度の整備と厳罰化
UAEは2016年、連邦法を制定し、絶滅危惧種を含む野生動物の個人飼育および所持を全面的に禁止しました。CITES附属書に掲載される希少種を個人が保有することは違法とされ、違反者は刑事罰の対象となり、高額の罰金または懲役刑が科されます。この法改正は、個人飼育の抑止に大きく寄与しています。
-
正規施設制度の導入
UAEでは「野生動物に関わりたい」「飼育や繁殖を行いたい」と考える市民に対し、政府認可の施設設立制度を設けています。個人での飼育は禁じられているが、国家の認可を受けた動物センターや研究施設として登録し、管理下で活動することは可能となっています。
また、市場や取引所に対しては定期的に抜き打ち検査を実施し、絶滅危惧種の販売が確認された場合には即時の営業停止措置が取られるそうです。
- 啓発活動と人材育成の推進
法制度の運用と並行して、UAEは教育および意識啓発活動にも注力しています。学校・大学・市場関係者を対象としたキャンペーンを通じ、野生動物の売買・展示行為が違法であることを伝えています。
また、パートナー機関との連携により、市場監視員や検査官を対象とした研修プログラムを実施しています。
その内容には以下のような実務的教育が含まれます。
- 絶滅危惧種の識別方法(CITES附属書掲載種の判別)
- 違法取引を検知するためのトレーニング
これにより、CITESの国内実施体制と現場の執行能力を強化しています。
- オンライン取引への監視体制とAI活用
近年のSNS普及に伴い、オンライン上での違法取引が世界的に課題となっています。UAEでは、通信事業を監督する国家通信規制当局が中心となり、AIアルゴリズムを用いた監視システムを導入しています。Instagramなどのプラットフォーム上で野生動物の販売や所持を示す投稿をAIが検出すると、自動的にページを閉鎖する仕組みです。
これにより、違法取引を早期に発見し、拡散を防ぐ体制が確立されています。
- 電子犯罪捜査部門による取締り
UAE警察(内務省および地方警察)には、電子犯罪捜査部門(Cybercrime Section)が設置されています。
同部門はオンライン上の環境犯罪も担当し、違法な野生動物販売・所持を行う個人を特定した場合には、捜査・逮捕・裁判まで一貫した対応を行う権限を有しています。違反者には高額な罰金または刑事処罰が科され、法の抑止力を高めています。
-
輸入規制と業者分類制度
UAEでは輸入段階においても厳格な管理が行われています。すべての動物・動植物の輸入にはCITES証明書の提出が義務づけられ、さらに輸入業者を分類する制度を導入しています。
これにより、
- 正規施設を有する専門機関のみ輸入許可の対象
- 個人は輸入申請資格を持たない
という仕組みが確立されています。 この制度により、飼育環境や設備基準を満たした者のみが動物を取り扱うことが可能となっています。
UAEのエキゾチックペットとメディアの問題
次にメディアとの関係についてのお話を紹介します。
日本をはじめ他国では、SNSインフルエンサーが野生生物を「ペット」として紹介する行為は、野生生物の需要を喚起し、社会的影響を及ぼしています。UAEでも同様の問題があったものの、法制度の厳格な適用により抑止されています。違法な動物を映像や写真で自慢する行為は「無許可所持」とみなされるだけでなく、「違法行為の助長」としても罰則の対象となります。
一方、野生動物を取り扱うことが認められているのは、政府認可施設を運営し、正式なライセンスを保持する者に限られています。これらの施設には、高い飼育条件や保険加入義務など厳格な基準が課されています。
さらに、テレビ番組や広告などのメディアも政府法に基づくコンプライアンス義務を負っています。違法飼育を助長する表現を行った場合、出演者のみならず放送局や制作会社も法的責任を問われることとなります。
湧き出てきた疑問
最後に、インタビューを通じて出てきた疑問は、大きく分けて2つです。
1点目は、「なぜ、野生生物の飼育に関する厳格な法律を制定することが可能だったのか」という点です。 2点目は、「その厳格な法律が実際に機能し、社会に受け入れられているのはなぜか」という点です。
日本では、エキゾチックペットを飼育する個人や施設が数多く存在しており、UAEで聞いたような法整備を進めようとすれば、強い反発が予想されるように思います。 そのような状況の中で、どのようにして法律が制定され、社会に浸透していったのか。反対意見を持つ人はいなかったのか。そうしたプロセスや背景に興味を持ちました。WCC期間中にこの疑問をヒアリングし、さらに深堀りしたいです。
Rooting Our Own Tomorrows (ROOTs)
宇都宮大学
杉山莉音