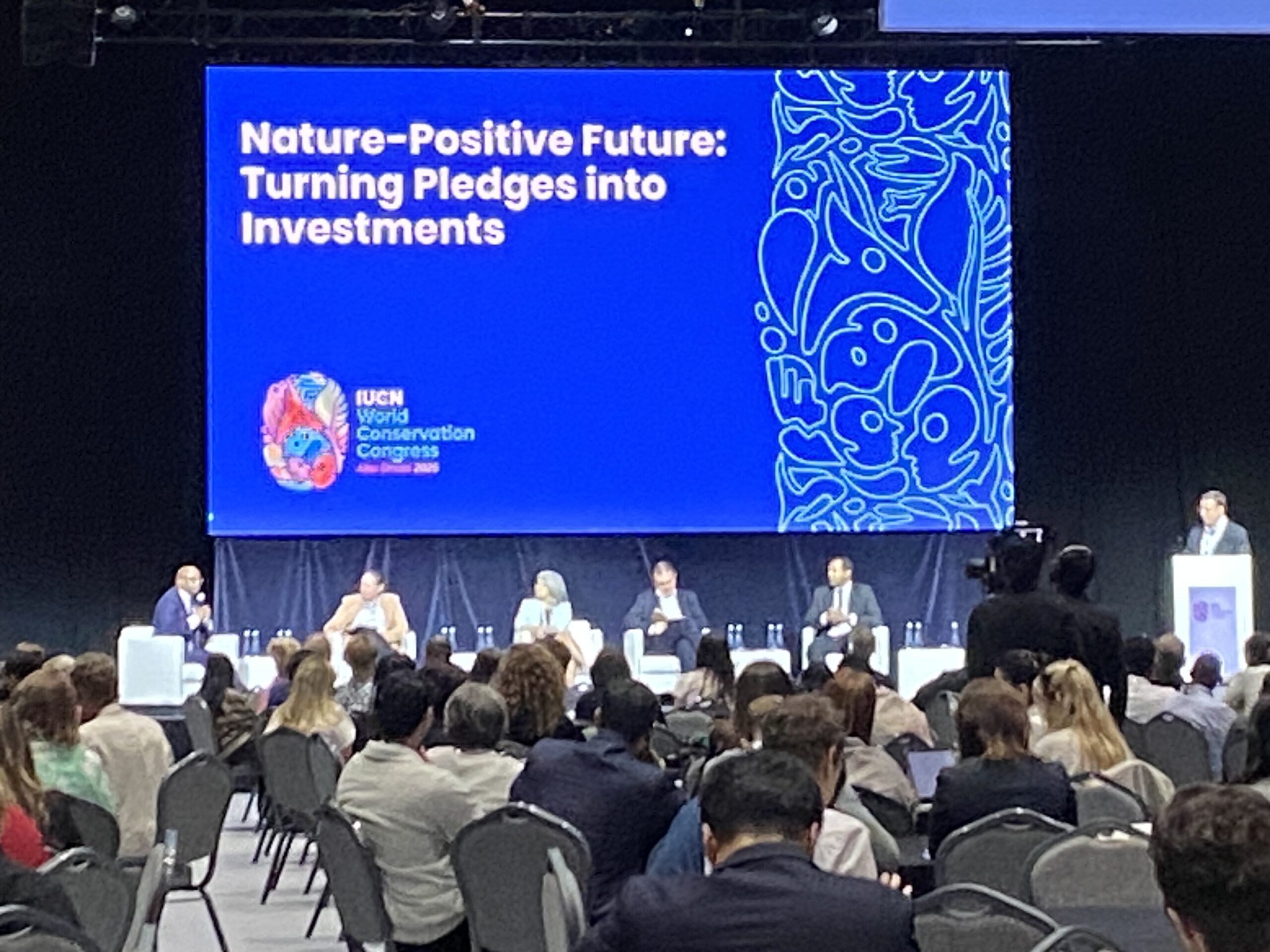「Community Fisheries Reserves -the road to 30×30 for freshwater ecosystems in KAZA」フォーラムに参加しました。淡水保全と地域主導の漁業管理の課題と可能性が見えてきました。
地域の背景と課題
アフリカ大陸のナミビア北東部に広がるカヴァンゴ川、クワンド川、リニャンティ川、チョベ川、ザンベジ川は、地域住民にとって生命線であり、世代を超えて食料、水、住居を提供してきた。これらの川沿いに暮らす「川の民」は、豊かな自然環境の中で誇り高く生活していた。
しかし、近年の人口増加、外部からの移住者の流入、そして違法漁業の過度な横行により、川の生態系は急速に悪化している。特に、外部の「ディーラー」と呼ばれる業者が、地元住民を雇って違法な網を使わせ、魚や水生生物を乱獲することで、川の資源は枯渇の危機に瀕している。加えて、気候変動の影響により農業も困難になり、住民の生活はますます川に依存するようになっている。
地域主導の解決策
このような危機的状況に対し、ナミビア自然財団と漁業・海洋資源省の支援のもと、地域住民が自らの手で川を守る取り組みを始めた。2015年、シクンガ地域とインパリラ地域のコミュニティは、ナミビア初の川の漁業保護区を設立。これによって、地元の「魚の守り手」が違法漁業を監視し、破壊的な漁法を排除する体制が整った。
この保護区では、魚の数が回復し、鳥や動物も戻ってきた。観光客が再び訪れるようになり、地域経済が活性化。保護区外の地域にも魚が広がり、全体の資源が改善されるという好循環が生まれている。
成功の要因と課題
この取り組みの成功には、地域の強いリーダーシップと住民の協力が不可欠である。各コミュニティはそれぞれ異なる課題を抱えており、持続可能な保護区を設立するには、地域に適した独自の計画が必要となる。
資金面では、遊漁権、漁業利用料、エコツーリズムなどを通じて収入を得ることが可能であるが、魚の守り手や監視員の育成・雇用には継続的な支援が求められる。また、教育活動を通じて住民の意識を高めることも重要な課題である。
今後の展望
現在、ナミビアでは20の漁業保護区が法的に認定されており、150km以上の川が保護対象となっている。この取り組みは、食料安全保障、文化・精神的遺産の保全、地域の誇りの回復に貢献しており、他地域への展開も期待されている。
地域主導の淡水資源保全は、単なる環境保護にとどまらず、コミュニティの持続可能な発展と自己決定権の確立にもつながる。今後は、より多くの地域がこのモデルを導入し、国際的な「30×30」目標(陸と海・淡水の30%を保護する目標)達成に貢献することが望まれる。
まとめ&コメント
ナミビアでは、地域住民が主体となって川の漁業保護区を設立し、違法漁業を防ぎながら自然と暮らしを守る取り組みが進んでいる。この活動は、淡水資源の回復だけでなく、観光や地域経済の活性化にもつながっている。地域主導の保全は、持続可能な未来への重要な一歩である。
自分自身は日本で釣りのライセンス制度を作りたいと考えているため、このような淡水での前例をもとに海水でも応用できるように模索していきたい。
小松大谷高等学校 山本 詩