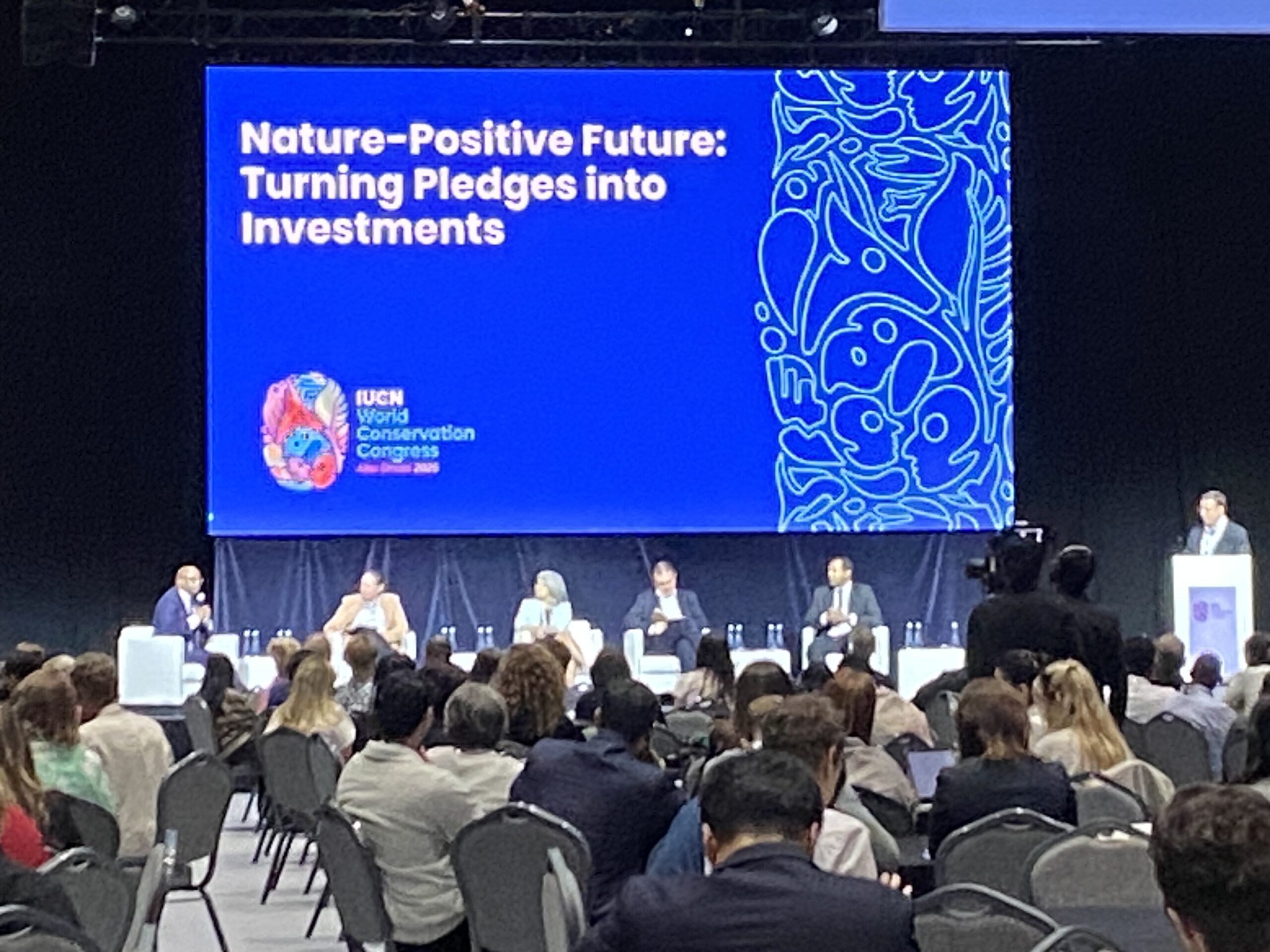-
はじめに
今回のブログでは10月11日、IUCN-WCC国際会議で行われた再生可能エネルギー関連セッションの内容をまとめてみました。このセッションでは、世界中の企業や政府機関、国際機関が集まり、再生可能エネルギーを導入する中で、生態系保全とどう両立させるかについて語り合っていました。
特に、風力や太陽光発電が生物多様性に与える影響や、地域社会への利益確保が大きなテーマでした。事例紹介やパネルディスカッションを通して、私自身もたくさんの学びを得ることができました。本ブログでは、企業や組織の取り組み、パネルディスカッションの内容、そしてNbS(Nature-based Solutions)の実践事例を整理し、最後に私の個人的な感想もシェアします。
-
企業事例紹介:再生可能エネルギーと生態系保全の統合
2.1 China Renewable Energy Engineering Institute
講演者:Jiali Zhang氏
Zhang氏は、太陽光発電産業の現状を、研究開発から施工・運用まで一貫して管理することで、ライフサイクル全体での環境負荷低減を実践している事例を紹介してくれました。
特に印象的だったのは、「PV(太陽光発電)+放牧」という方法です。砂漠化抑制や植生復元、土壌水分改善など、生態系を守りながら地域社会の利益も生み出す取り組みが紹介されていました。こうした実践を見て、技術と自然保護がうまく融合できることを改めて感じました。

2.2 SPIC Huanghe Hydropower Development Co., Ltd.
講演者:Yu Miao氏
Yu氏は、PVセルの研究開発から発電所建設、運用・保守、部品リサイクルまでを含む、グリーン・サーキュラー型産業チェーンを構築した事例を紹介しました。
青海省では、世界最大級のPV産業パークやハイブリッド水光発電所を整備し、湿地面積が600 km²増加、植生カバーが150ヘクタール以上拡大、砂漠化地が100 km²以上減少するなど、生態系へのプラス効果が観測されています。また、一帯一路イニシアティブを通じて、中東(UAE、サウジアラビア、クウェート)でも1.13 GW超のプロジェクトを展開しています。
こうした数字を見ると、単なる環境保護ではなく、具体的な成果が出せる取り組みだと実感しました。
2.3 Shell社・TotalEnergies社:グローバル事例
- Shell社(Karen Westley氏)
BlauwwindおよびCrosswindの洋上風力プロジェクトでの、海洋生物保全措置(Above water / Under water measures)が紹介されました。
- TotalEnergies社(Astrid Delporte Sprenger氏)
2030年までに再生可能エネルギー100 GWを目標に、地域参加型の太陽光・風力プロジェクトを推進しています。アグロPV(農業と太陽光の統合)により、地域の所得向上、農地保全、植生回復を両立。Tutly Solarプロジェクトでは、カメの移動保護や放牧輪番制、地域住民への教育も行い、生物多様性保全と再生可能エネルギー生産の共益を実現しています。

2.4 政府・国際機関事例
- EBRD(Adonai Herrera-Martinez氏)
再生可能エネルギー開発における環境・社会配慮プロジェクトへの資金提供事例を紹介しました。 - Qinghai Development and Reform Commission(Ma Hao氏)
「PVと砂漠管理・生態的畜産」プロジェクト、「生命の鳥の巣」(鳥類保護)、そして「魚類リフターシステム」(遡上魚保護)など、再生可能エネルギーと生態系・地域社会利益を統合した取り組みを報告しました。


こうした取り組みを見ると、政策・企業・地域が連携することで、自然と共生するエネルギー開発が現実になっていることがよく分かります。
-
パネルディスカッション:持続可能な再生可能エネルギー開発
パネリスト:Aonghais Cook氏(TBC)、Sophie Depraz氏(Ipieca)、Jinlei Feng氏(IRENA)、Libby Sandbrook氏(Fauna & Flora)
3.1 主な発言
- Jinlei Feng氏(IRENA)
政策統合、技術移転、財政的インセンティブの重要性を指摘。再生可能エネルギーと生物多様性の目標をどう統合するか、業界間の知識格差やコスト面の課題解決の必要性を強調。 - Libby Sandbrook氏(Fauna & Flora)
科学的知見を活用した早期段階での介入、ステークホルダー間の信頼構築、NGOを通じた協働の重要性を強調。 - Sophie Depraz氏(Ipieca)
企業のベストプラクティス共有、ESG統合、地域社会利益の同時実現、Holisticなアプローチの大切さを指摘。 - Aonghais Cook氏(TBC)
劣化地開発での地域専門家との協働、知見共有による成功事例のスケーリングの重要性を説明。
パネルを聞いていて、「多様な立場の人が協力すれば、再生可能エネルギーの開発と自然保護は両立できるんだ」と実感しました。
-
中国企業によるNbSベストプラクティス
講演者:Deng Mingwei氏
NbS(Nature-based Solutions)は、地球規模の複合的危機の中で、人と自然の共生を目指す新しいアプローチです。12件の代表事例では、事業運営への深い統合、低影響開発、技術活用による修復効率向上、そして多様なステークホルダーとの協働が示されていました。
企業が積極的にNbSに関わることで、SDGs達成への貢献も期待できることを学び、私自身も非常に刺激を受けました。

-
個人的所感
私は局地風現象を研究している修士学生です。風力や太陽光など再生可能エネルギーに強い関心があります。研究室の指導教員のもとで国内外の企業を訪問した経験もありますが、今回のセッションに参加して、多様な企業や国際機関の取り組みに触れることで、改めて以下のことを感じました。
- 風力発電の生態影響
低炭素である一方、騒音や振動、鳥類などの生息地への影響が大きく、計画段階で科学的データに基づく評価が不可欠です。 - 太陽光発電の植生管理
パネル下での放牧やアグロPVなどの工夫はありますが、光の遮蔽による植生退化や土壌水分への影響など、潜在的リスクは残ります。地域環境に応じた長期モニタリングが必要です。 - 研究課題の示唆
局地風モデリングの知見を活用して、風力発電の立地選定や設計段階での生態影響評価の精度向上に貢献できます。また、太陽光発電と土地利用・植生管理の相互作用を組み合わせた研究も有効だと感じました。
セッションを通して、「再生可能エネルギーと生態系保全の両立は、決して理想論ではなく、企業・地域・国際機関が協働すれば実践可能」ということを実感しました。将来的には、自身の研究を通して、局地気象環境や再生可能エネルギー導入による生態系影響評価を統合した研究に挑戦したいです。
-
結論
再生可能エネルギー開発において、生物多様性保全と地域社会利益の両立は十分に実践可能であることが確認できました。太陽光・風力・水力発電の企業は、事業運営に生態系保護措置や地域参加型の取り組みを組み込み、持続可能な開発を進めています。政策支援や国際機関との協働も重要です。今後は計画段階から生態系への影響評価を取り入れ、科学的根拠に基づく設計・運営を行うことが求められると感じました。
筑波大学 地球科学学位プログラム 修士1年生 SIQINGTUYA
登壇者一覧
- Ms. Jiali Zhang – China Renewable Energy Engineering Institute
- Mr. Miao Yu – SPIC Huanghe Hydropower Development Co., Ltd.
- Ms. Karen Westley – Shell
- Ms. Astrid Delporte Sprenger – TotalEnergies
- Mr. Adonai Herrera-Martinez – European Bank for Reconstruction and Development
- Mr. Ma Hao – Qinghai Provincial Development and Reform Commission
- Mr. Aonghais Cook – Consultant
- Ms. Sophie Depraz – Ipieca
- Mr. Jinlei Feng – IRENA
- Ms. Libby Sandbrook – Fauna & Flora
- Mr. Deng Mingwei – China Sustainability