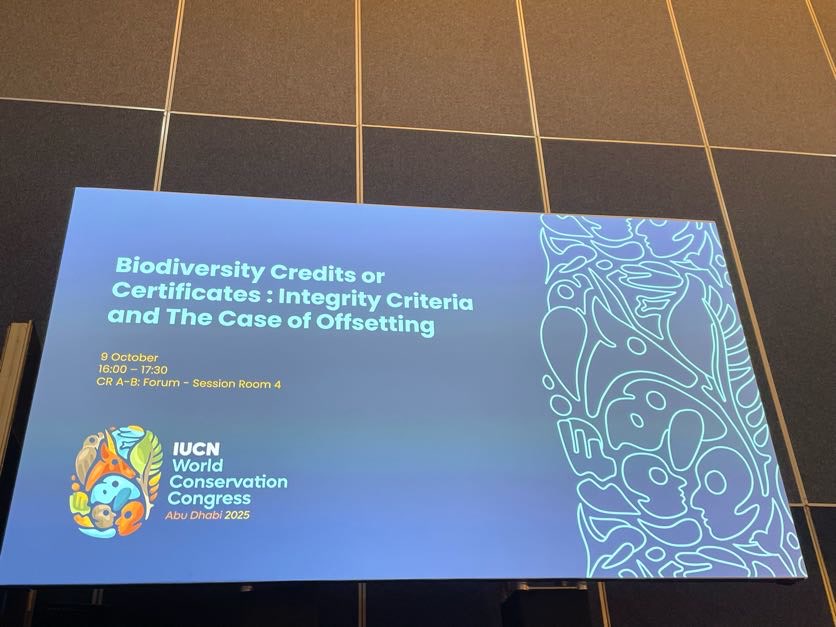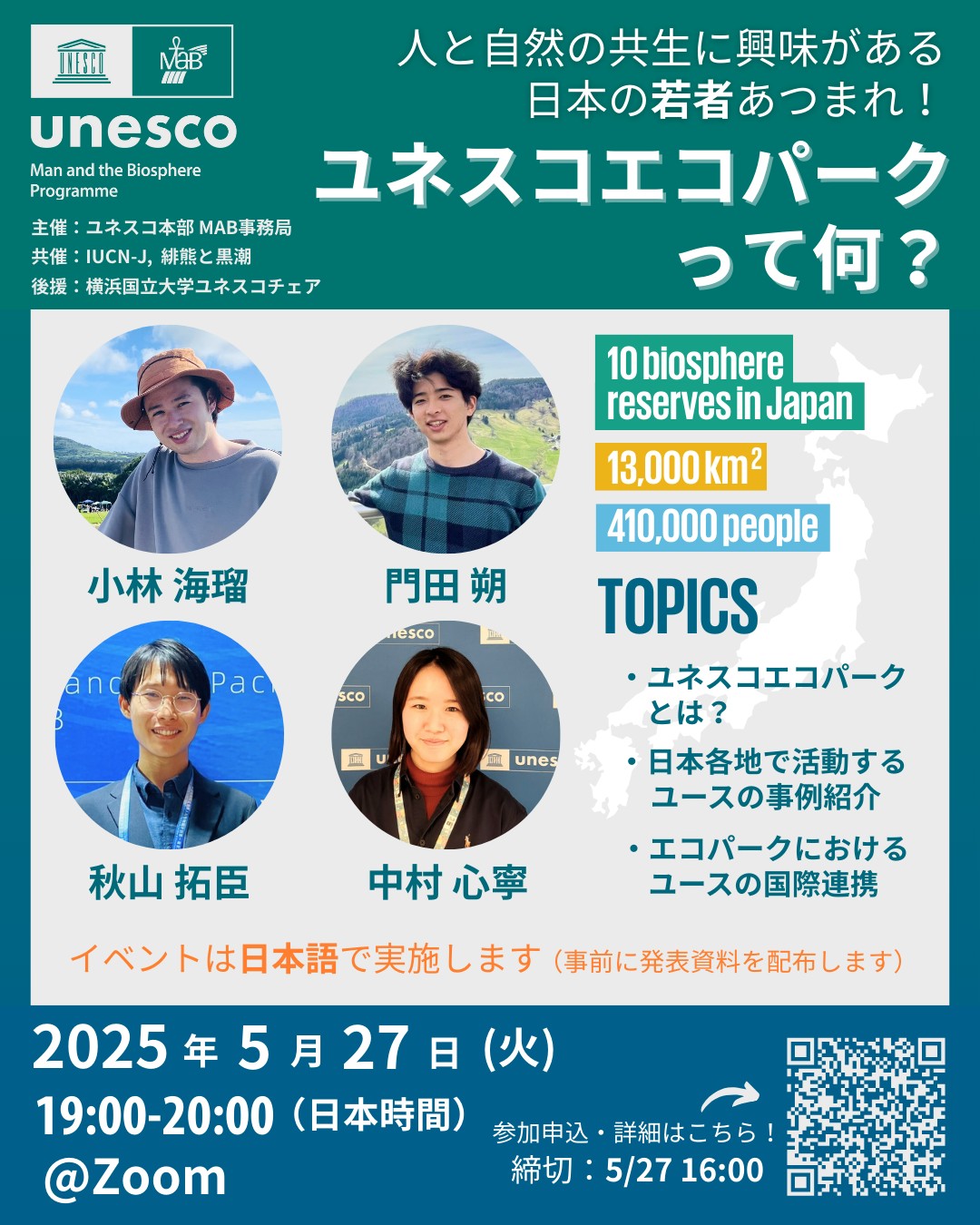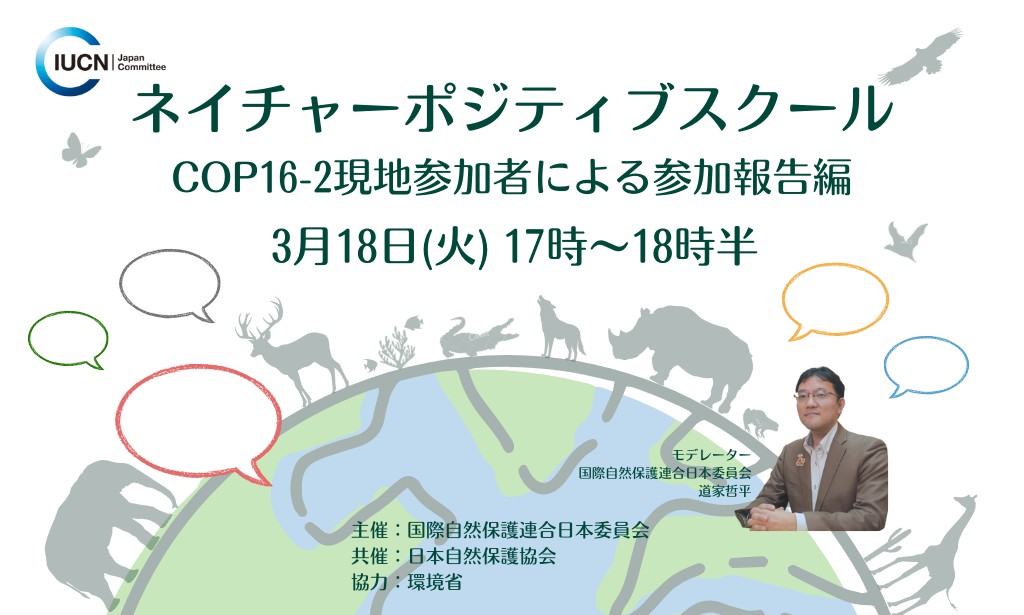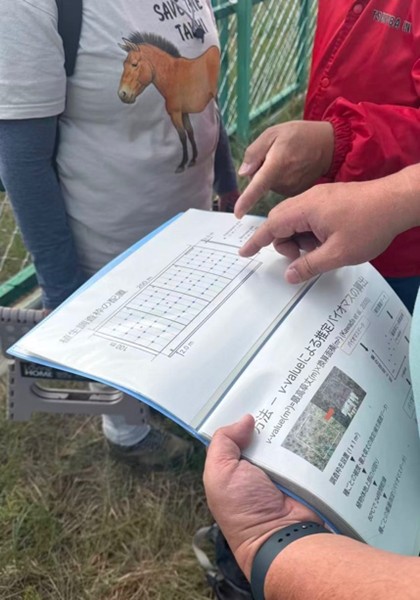1.セッションの概要
本セッションは10月10日、France Pavilionにて開催された。「Sport : an unexpected lever to protect endangered biodiversity(スポーツ―絶滅危惧種保護のための一風変わった切り口:筆者訳)」というテーマのもと、スポーツが生物多様性保全の推進に果たす新たな役割が議論された。セッションでは、IUCN、Play for Nature、Sahara Conservationなど複数の団体からスピーカーが登壇し、スポーツの社会的影響力を活用した実践例や、国際的枠組み「Sport for Nature」イニシアティブが紹介された。
2.なぜこのセッションに参加したか
本セッションは私が渡航前にプログラム一覧を確認した際、特に関心を持ったセッションの一つであった。「スポーツ」と「絶滅危惧種の保護」という一見相入れないテーマがどのように結びつくのか、知りたいと思ったからである。
自然保護の現場に関わる中で感じる課題の一つに、活動に熱心な人々と一般市民との間に存在する知識や関心の隔たりがある。この溝を埋めるための新しいアプローチに関心があった。
言うまでもなく、スポーツは多くの人々の生活に根付いている。もしスポーツを通じて絶滅危惧種の保護や生物多様性への理解を深めるきっかけを提供できるのなら、この隔絶の問題を和らげ、世界中の人々がより一体となって自然保護に関わることができるのではないかと考えた。
また、WCC初日に行われたオープニングセレモニーではモロッコ王女殿下がスポーツの力について言及していたこともあり、このテーマが今後世界的な潮流となる可能性を感じた。そうした背景から、スポーツと自然保護の連携がどのように展開されるのか注目したいと考え、参加を決めた。
3.セッションの内容
登壇者たちは、スポーツがもつ社会的影響力と感情的な力を活かすことで、人々の自然保護への意識と行動を変えることができると強調した。特に「世界人口の約15%が現役または元アスリートである」というデータが紹介され、スポーツが社会変革を促す潜在力を持つことが印象づけられた。スキーやサーフィンなど自然を舞台とする競技が気候変動の影響を受けやすいことも挙げられ、スポーツと環境の相互依存関係が明確に示された。
フランスの環境団体Play for Natureの代表者からは、スポーツ施設の持続可能性向上や環境教育の普及を目的とした取り組みが紹介された。スポーツ組織の環境認証制度を通じて行動変容を促す仕組みや、アスリートの社会的影響力を活用した啓発活動が進められており、スポーツ界が自らの枠組みを通じて自然保護に貢献する新しいモデルとして注目された。
また、IUCNの代表者からは、オリンピック委員会や生物多様性条約事務局などと連携し、2030年までにスポーツ分野で自然にポジティブな行動を拡大することを目的とした「Sport for Nature」イニシアティブが紹介された。この国際的枠組みでは、署名団体が自己評価ツールを用いて環境配慮の進捗を確認し、小さな実践の積み重ねによって大きな変化を目指す仕組みが整えられているという。
さらに、アフリカの自然保護団体Sahara Conservationの代表者からは、地域社会がスポーツを通じて環境教育に取り組む事例が報告された。ニジェールで実施されたプログラムでは、子どもたちが地元の動物の名前を冠したチームをつくり、ごみ拾いやリレー競技を通して生態を学ぶ活動が行われている。楽しみながら環境意識を育むこの取り組みは、スポーツが地域社会の誇りや連帯感を生み出す有効な手段であることを示す好例であった。
このように、本セッションでは「スポーツが生物多様性保全の予想外の味方になり得る」という理念のもと、国際的・地域的レベルでの多様な実践が共有された。スポーツのもつ熱量と影響力を社会変革へと結びつける具体的な枠組みが示された点に、大きな示唆を得た。
4.コメント
総じて、スポーツを自然保護と結びつけることで、現在スポーツに関心をもつ多くの人々を自然保護へと導く可能性があるという議論に大いに納得した。
その一方で、今回強調されていた「人気のあるスポーツと自然保護を結びつけることで多くの人々の関心を集める」という前提から、「新たなスポーツを創出する」という方向性へと展開している点には、ややズレを感じた。ただし、最後に共有された活動資料によれば、彼らは既存のスポーツとの連携と新たなスポーツの創出の両軸で取り組みを進めているとのことであり、その点で一定の整合性が見られる。
スポーツは人々を結びつける最も身近な活動であり、自然保護への関心を高める入口として極めて有効である。特別な知識がなくても、スポーツを通して自然に触れ、環境について考える機会を得られる点に大きな可能性を感じる。
ただし、活動そのものが目的化し、行動だけが先行してしまう懸念もある。自らの取り組みが自然や地域にどのような影響を及ぼしているのかを常に意識しながら進めなければ、それは真に持続可能な取り組みとは言えないだろう。
彼らが主催するスポーツを単なる身体的体験に終わらせず、「学び」や「理解」へとつなげ、行動と内省を往復させる仕組みづくりに今後注目したい。スポーツが生み出す熱量や共感をきっかけに、人々が自然と向き合い、その価値を理解していく流れが広がることを期待する。
この点については、現在LinkedInを通じてPierre氏に意見を伺っており、続報があれば改めて共有したい。
筑波大学 世界遺産学学位プログラム M1 作森元司郎
登壇者一覧(IUCNのサイトより)
- Mrs. Anne MEADEB(Play for Nature)
- Mr. James HARDCASTLE(IUCN)
- Mrs. Violeta BARRIOS AQUINO(Sahara Conservation)
- Mr. Julien PIERRE(Play for Nature)
共有資料:https://qr.scanned.page/uploads/pdf/2MdraX_46d8d3d8bcfc4c6d.pdf